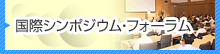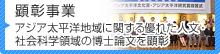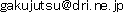第23回「アジア太平洋フォーラム・淡路会議」国際シンポジウムの概要
第23回「アジア太平洋フォーラム・淡路会議」国際シンポジウムの概要

- プログラム
-
- 日時
2022年8月5日(金)
13:00~17:35 - 場所
兵庫県立淡路夢舞台国際会議場
(兵庫県淡路市夢舞台1番地) - テーマ
「コロナ危機・ウクライナ危機後の世界と日本」 - 内容
- ○開会挨拶
- 井植 敏
- (アジア太平洋フォーラム・淡路会議代表理事)
- ○歓迎挨拶
- 片山 安孝
- (兵庫県副知事)
- ○第21回アジア太平洋研究賞授賞式
第19~20回アジア太平洋研究賞授賞者紹介 - ○淡路会議開催趣旨説明
- 片山 裕
- (神戸大学名誉教授)
- ○記念講演
- コーディネーター:五百旗頭 真(ひょうご震災記念21世紀研究機構理事長)
- ◆記念講演1
- 「ウクライナ危機が問いかけていること」
- 講師:船橋 洋一
- (公益財団法人国際文化会館グローバル・カウンシル チェアマン/元朝日新聞社主筆)
- ◆記念講演2
- 「パンデミックと日本の現場・国際社会」
- 講師:砂川 富正
- (国立感染症研究所実地疫学研究センター長)
- ◆記念講演3
- 「激動の時代とアジア経済の行方」
- 講師:澤田 康幸
- (東京大学大学院経済学研究科教授/前アジア開発銀行チーフエコノミスト)
- ○開会挨拶
- 日時
- ◇記念講演1 「ウクライナ危機が問いかけていること」概要
- 船橋 洋一(公益財団法人国際文化会館グローバル・カウンシル チェアマン/元朝日新聞社主筆) 1.ウクライナ戦争が日本に与える意味
2月に始まったウクライナ戦争は今なお続いている。しかし、時代錯誤とも感じるこの戦争は、急に起こったわけではなく、ロシアにとってはソ連崩壊、ウクライナ独立、2014年のクリミア併合等に伴う民族主義的思想の煽動、ウクライナにとっては、独立後の政治体制をヨーロッパ寄りにするかロシアとの関係を重視するか、ロシア系住民やロシア語の位置付けなどのアイデンティティの問題等、多数の伏線があった。
これらは地政学、さらに言えばレアルポリティーク(権力政治)の問題である。今回、ロシアはヨーロッパ、特にドイツに対して天然ガスの供給を停止するという制裁を行う一方、世界各国から金融をはじめとする制裁を受けている。制裁された国は、制裁されたことを忘れない。アフリカやアジア、南米といったグローバルサウスの国々や、中国やインドのような地域大国の多くが、今年3月2日に国連総会で行われたロシア非難決議で棄権し、4月7日、国連人権委員会におけるロシアの理事国資格を停止する決議が可決された際は、トルコやメキシコなど59カ国が棄権した。棄権国の多くは経済制裁を受けた経験がある。ロシアのウクライナ侵攻に最も脅威を感じているバルト海の国々では、フィンランドとスウェーデンが、これまで中立国の立場を保ち、NATO(北大西洋条約機構)には未加盟だったのが、一気にNATO加盟を決定した。
一方、日本は戦後間もなくの1950年に大きな選択を迫られたが、講和を受け入れるという正しい選択をした。もし中立を選んでいたら、日本はもたなかったであろう。
2.地政学的重圧を受ける日本
地政学とレアルポリティークの話をしたい。ロシアにとってウクライナは地政学的に最も重要な地域である。バルチック艦隊の寄港地として知られるバルト海沿岸のカリーニングラード(ロシアの飛び地)が、リトアニアやポーランドを経由しないと行けないように、黒海に面したウクライナのクリミア半島も、ロシアにとって重要な勢力圏で、地理の専制(tyranny of geography)とも言える過酷で苛烈な地政学的状況にある。
日本や台湾も、地政学的な重圧にさらされている。日本も台湾も、アリューシャン列島から北海道、日本列島、南西諸島、台湾、フィリピン、ボルネオ島、インドネシアに至る「第一列島線」の真ん中に位置している。中国は日本の与那国島や宮古島、台湾は目障りなバリケードのようで、窮屈に感じている。日本と台湾は、「第一列島線」でウクライナと同様な地政学的リスクを背負っている。「第一列島線」を共有していることが「台湾有事は日本有事」の構造的背景になっている。
3.中露接近にどう向き合うか
中国とロシアはいずれも専制主義(authoritarian)で、日本のような民主主義国とは政治体制が異なる。その中で努力して付き合い、共存し、もめ事を制御しなければならない。
今、中国とロシアは安全保障上の利害が非常に深く一致しており、条約を基にした同盟ではないものの、深い提携、協商関係を構築している。今年2月4日に出された中露共同声明は、英語で5,000字以上の長文で「無限の友情」や「無限の協力」といった言葉を使い、事実上の準同盟宣言と呼べる決意表明である。また、中国はベトナムとの領土交渉を成功させ、ロシアともエリツィンの時代に領土問題を解決し、その後の中露関係の安定につなげている。さらに、中国に取って深刻なエネルギー問題についても、中露で相互補完関係を築いている。ロシアから天然ガスパイプライン「シベリアの力1」を引き、今年2月に中露共同声明を発表した時には、モンゴル経由の2,600kmのパイプライン「シベリアの力2」によるガス供給量拡大に契約した(2024年着工、2030年頃完成予定、30年強の長期契約)。
現在のロシアは、中国との協商関係を安定化させる一方、アメリカに対しロシアの専制主義を崩壊させるのではという不信感や敵がい心を持っている。中露両国の関係は長期化し、そのこと自体が日本や欧米を中心とした民主主義国あるいは近隣国に非常に難しい問題をもたらすであろうと思われる。
両国とも核保有国であり、ユーラシアの端の半島には北朝鮮というもう一つの核保有国がある中、日本は二正面外交を強いられ、さまざまな面で中露に対して難しい立場に立ち、熾烈な状況に立ち向かわざるを得ない。
4.長期化するロシアへの経済制裁
今は地政学的目的のために経済をパワーとして使う時代になっている。この戦争を終わらせるため、どこかで休戦協定を結び、平和協定という出口戦略を思い浮かべるために今回の経済制裁体制は必要であるが、残念ながら非常に長期化すると考えられる。
ロシアが半導体などさまざまなものが輸入できなくなっていることは確かに効いている。戦前の日本も輸入ができないために持たなくなった。特に資源やハイテクの輸入分野の経済制裁を進めている。今回の制裁は、常任理事国であり拒否権も持っているロシアが相手のため、国連憲章第41条に規定されている経済制裁ではない。ただ、国連は、経済制裁を国際平和安定のための正当な手段であると憲章に明記している。軍事力を使わず、経済制裁を使うインセンティブは高まっている。
一方、今回の国連のロシア非難決議に関しては、棄権国がとても多い。3月2日の非難決議では棄権国35カ国のうち32カ国、4月7日の国連人権委員会の理事国資格停止決議にでは棄権国59カ国のうち47カ国は、中国から戦略的なインフラ投資や融資を受けている国々、中国の「一帯一路」沿線国(Belt and Road Initiative:BRI)である。
世界199カ国のうちロシアへの経済制裁のレジームに加わっているのは、日本を含む民主主義国の37カ国だけで、多くの国々は棄権国あるいは反対国である。IMF(国際通貨基金)の調査では、棄権国のうち53カ国が債務危機または債務危機寸前であり、グローバルサウスの国々、東南アジアなどの諸国は、どちらか選択を迫られること自体を拒否していくと思われる。そうした国々と国際秩序安定のビジョンを共有し、一緒に何ができるのかを考えるような、新しい外交を進めるなければならない。
5.揺らぐ国際秩序の中で
戦後70年以上かけて、アメリカを中心に築かれた、自由で開かれたルールベースドの国際秩序「LIO(liberal international order)が今、非常に揺らいできている。日本、韓国、中国、インドなど多くの国々がその裨益を受け、戦後の奇跡ともいえる長い平和を築いてきたが、LIOが崩れればどうしても地政学的なレアルポリティークが生まれ、国際秩序は固定相場制から変動相場制に代わったような取引的なものになっている。これは日本にとって非常に由々しきことである。国際秩序が安定していた時、日本は1902年に日英同盟を結び、かつて戦争相手だったアメリカと同盟国となり、国際秩序の安定の中で繁栄してきたが、秩序が崩れれば非常にもろい国である。
1968年、西ドイツを抜いて世界第2位の経済大国となった後の1972年、後にカーター政権で国家安全保障問題担当の大統領補佐官となったアメリカの国際政治学者ズビグネフ・ブレジンスキーが、著書『fragile blossom(ひよわな花・日本)』の中で「日本の経済成長は確かに素晴らしく、あっという間に経済大国になった。しかし、ニクソンショック後の日本を見ていると、外部の秩序の変化に非常にもろい。自らコントロールできないことの余波がこれほど大きく作用する国はそうはない」と述べている。われわれはこの観点を忘れているのではないか。
昭和の時代、日本はみんながよく働き、戦後復興したことで経済大国になったが、その繁栄は背景にあった国際環境や国際秩序によって許され、機会を与えられた部分が大きかった。中国、韓国も同様に繁栄したが、今はそれが大きく暗転している。
安全保障の一番の黒字国はアメリカで、南北の国境をカナダとメキシコとしか接しておらず、東西を大西洋と太平洋に挟まれている。アメリカがこれだけグローバルに国力・戦力を投射できる国になったのは、安全保障の黒字構造が大いに影響している。一方、ドイツやポーランドは8カ国、ロシアと中国はいずれも14カ国と国境を接している。国境をたくさん持つユーラシアの国々は、地政学的に安全保障の赤字国である。
日本は、東シナ海のおかげで中国の影響力を相当防ぐことができ、海によって物理的に遮られ、時間を稼ぐことができるので、朝鮮半島と比べてはるかに有利である。第二次世界大戦後もブレトン・ウッズ体制、国連のシステム、何よりも日米同盟という国際秩序のおかげで安全保障の黒字国だった。しかし、今はその黒字がどんどん減っている。肝心のアメリカがどこまで国際的な抑止力を構築し、コミットメントを維持できるのか。TPP(環太平洋パートナーシップ協定)からの撤退はトランプだから強行したという見方もあるが、バイデン政権でもその路線は踏襲され、TPPには復帰しないと明言している。アメリカがマーケットアクセスを提供できないことによって、そこに空白が生まれている。
安倍政権下の日本は、TPPの代わりに発効されたCPTPP(環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定)の交渉においてリーダーシップを発揮した。QUAD(日米豪印戦略対話)もサミット開催まで持っていったので、長期的な一つの大きな枠組みになっていくと思われる。QUADも包含すると思われるFOIP(自由で開かれたインド太平洋)という概念も、中国と競争はするけれども、同じ原則をシェアするならば一帯一路に関しては協力できるものは協力していこうという姿勢をとっている。アメリカにトランプ政権という非常に特異な政権が生まれ、アメリカがTPPから撤退したことで空白が生まれたこと、その空白を埋めることをアメリカが認め、あるいは認めないまでも日本にある程度やらせてもいいという姿勢だったこと、そして中国がトランプに対する保険として日本との関係もある程度良くしようとしたこと、日本はこれらの状況をうまくとらまえて空白を埋めることができた。
国際秩序が崩壊し、新しいものは生まれず、むしろ中国がオルタナティブを出そうとする中、安倍政権は「積極的平和主義」といって、自ら当事者意識を持って、自由で開かれた国際秩序に積極的に参画し、構築していった。日本はルールメーカーになれるほどの大国ではないけれども、ルールメークの環境をつくるルールシェイパーにはなれる外交を行った。国際秩序が崩れ、安全保障の黒字が減っている時にはとても重要な外交であった。
6.「国民安全保障国家」を目指せ
ウクライナ戦争で見えてきた課題を日本に照らして考えてみると、まず経済制裁とは本当に恐ろしいものである。戦前の日本は、アメリカから石油制裁を受けた。あの制裁によって日米戦争が起こったわけではないものの、日米外交交渉が進まなくなった。
経済相互依存があれば平和を維持しようとする意志が働き、関係が安定するが、どちらかが依存する非対称性が生まれると、相互依存の武器化(weaponization)が起こりやすくなり、経済制裁に振り回されると、自国第一主義の方向へどうしても移行し、全世界がよりローカルでリージョナルな枠組みに向かう。その結果、普遍的な原則やルールが守られにくくなるリスクが生じ、経済制裁を予防するために先制攻撃的に資源を奪うような争奪戦になって国際秩序が破壊される恐れが生じる。
日本は経済制裁の怖さを考えておかなければならない。日本は他国に経済制裁を振りかざせるほど体力がない。エネルギー自給率はたった11%と、G7の中でも断トツに低い。アメリカやカナダのような100%以上の国は例外にしても、次に低いイタリアでも26%、ドイツは45%ある。エネルギー一つとっても日本はいかにももろい。
また、戦前の日本は軍が民間のシーレーンを守れず、逆に民間の船が軍に徴用されるという悲劇的な状況が起きた。ネットワークシステムに悪意を持ったバグを埋め込まれることへの警戒感を持ち、経済のレジリエンスにアメリカとともに取り組む必要はあるが、日本はそもそもその前にシーレーンも含めエネルギーや資源の経済安全保障において手当てすべきことがたくさんある。
サンフランシスコ条約締結後、アメリカの政治家ジョン・フォスター・ダレスは、「アメリカは地政学のくびきから世界を解き放った」と言った。実際、アメリカが中心となって構築した戦後の国際秩序が、戦前のような地政学的葛藤を相当程度抑え込んできたが、日本の安全保障や経済安全保障は、アメリカ頼みだけで守れなくなっていることを正面から見据える必要がある。世界のパワーバランスを維持し、国際秩序を積極的に構築していく上で日本の役割は大きくなっており、今後日本は安全保障を政策としてより貫徹させていくべきである。日本は、気候変動やパンデミック、自然災害という大きなインパクトのあるリスクに対する安全保障を含めた「国民安全保障国家」をつくっていく必要がある。
- ◇記念講演2「パンデミックと日本の現場・国際社会」 概要
- 砂川 富正(国立感染症研究所実地疫学研究センター長) 1.実地疫学研究センターの紹介
脇田隆字を所長とする国立感染症研究所(以下「感染研」と記す)には、研究部やセンターが配置され、大部分が病原体などの基礎面の研究を行っているが、感染症疫学センター、感染症危機管理研究センター、そして私がセンター長を務める実地疫学研究センターの三つが他の部と異なる性格を持つ。
実地疫学研究センターの中に1999年9月、FETP(実地疫学専門家養成コース)が設立された。1996年、大阪府堺市の学校で腸管出血性大腸菌O157による集団食中毒が発生し、約8,000人が感染したが、当時はこうした大規模な事例に対し、特に国が自治体を支援する仕組みや権限がないことが問題になった。そこで、1999年に感染症法が施行され、2年間の実務研修を行うFETPが設置された。実地疫学(field epidemiology)では、仮説がない状態で問題が勃発した時、その全体像を把握し、どういう問題が起きているのかという仮説を現場で設定し考える。その学問を行う人たちを実地疫学者(field epidemiologist)と呼ぶ。
FETPは、米CDC(疾病管理予防センター)の疾病情報サービス(Epidemic Intelligence Service)というプログラムをモデルにし、ロゴの穴の空いた靴のように、穴が開くほど現場を歩いて調べる「病気の探偵」の養成を目指している。現在20人が在籍し、およそ8割が自治体から派遣された方々であり、私はここの1期生である。
こうした実地疫学専門家(以下「専門家」と記す)は、感染症の危機管理事例を迅速に探知して現場で対応しているほか、実際に起こった事例について、今はこういう状況だからこんな対策を取れば次にこんな展開になる、取らなければこんな展開になるということをいろいろな情報や知見を基に分析し、現場の対応に芯を与えて、状況が改善するまでの対応をバックアップする。この方法が、新型コロナ感染症対策において有効であった。専門家は現場の肌感覚を大事にしており、現場で得られた情報を自治体の首長や政府の必要な方々に提供し、市民へのコミュニケーションを促進している。
世界では、現在75のプログラムで2万人の専門家が各国の公衆衛生施策に従事しているが、日本ではこの22年ほどの間にFETP修了者がまだ100名にも達していない。WHO(世界保健機関)の試算によると、日本の人口に対して600人の専門家が必要だが、年間約100人を養成しても、あと6年ぐらいかかる。そこで国からは各都道府県、保健所設置市および特別区(計155自治体)に1名ずつ、すなわち155名に達するように努力するよう指示をいただいている。
2.新型コロナウイルス感染症パンデミックとの関わり
日本の新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の初期を振り返る。2020年2月の第1回専門家会議では「(当会議は)日本で新型コロナウイルスに対応するための基本的な考えを、社会・経済機能への影響を最小限としながら、感染拡大を抑制する効果を最大限にする方針とし、政府に助言した」と述べられている。日本は当初からコロナをゼロにするのではなく、社会・経済機能を回しながらコロナ対策を行う「ウィズコロナ」の方針を示していた。専門家会議では、日本における初期のCOVID-19対策の根幹に、①クラスターの早期発見・早期対応、②医療体制の確保、③市民の行動変容の3つを挙げている。
同じ頃、ヨーロッパ各国では、感染者の強制隔離など強い権限で人の行動を抑制した。新たな法制度の制定、憲法の緊急事態条項などの適用変更、特別権限の付与など、かなり強力な対応がなされていた点が日本との大きな違いである。例えばフランス政府は、封じ込め対策として外出に必要な書類を持っていない者に罰則規定を設けるなど、日本のように自主的な抑制に期待するのではなく、警察なども動員した形で厳しく対応した。
日本では、いわゆるステージⅣ、「爆発的な感染拡大および深刻な医療提供体制の機能不全を避けるための対応が必要な状態」になった時に「緊急事態宣言」が都道府県単位で発出され、その手前の段階に「まん延防止等重点措置」が取られた。また、飲食店への対応が重視され、時短と休業の命令・要請に、違反すれば30万円以下の過料が課された。住民には外出自粛が要請された。発出、期間延長、区域変更時には国会への報告が義務付けられたが、全般的に他の国に比べて厳しくなかった。その中で、公衆衛生上の対策の根幹がクラスター対策である。クラスターを「ヒトヒト感染を起こすような状況下で便宜的に5人以上が感染を起こした集団と認識される場合」と定義した。
全国の保健所が中心となってクラスターを早期に見つけ、迅速に対応し、感染研は専門家グループとしてその対応について支援を行ってきた。当初の感染拡大の状況が随分変わっていく中で、クラスター対応を中心とした対策が結果的に長く続き、成果も上げたが、保健所と公衆衛生業務に携わる方々への業務負荷が非常に高まっており、どの状況でクラスター対応をするのか、やめるのかを検証する必要がある。
積極的疫学調査の実施要領には、コロナに限らず重要な感染症対策として「感染源の推定、濃厚接触者の把握と適切な管理を行うことによって感染伝播拡大阻止に努めることが重要である」と書かれている。それを各保健所が進める上で、感染研は、2020年2月に政府が発足させた「クラスター対策班」の「接触者追跡チーム」に入り、他の大学や専門家のグループと情報連携を行いながら対策を進めてきた。
新型コロナはヒトからヒトに感染する中でクラスターが発生し、あるクラスター内の感染者が次のクラスターの始まりになるので、この感染者を隔離してストップさせれば、次の大規模感染を防げる。例えば10人のクラスターだった場合、そのうちの9人までは誰にも感染させていないが残りの1人が多くの人に感染させている傾向があった。その傾向は「三密」と呼ばれる特徴を持った行動から発生する。その約1割の対応すべき人たちに集中的に対策を取ることで、クラスター対応として成功するだろうと目された。
また、感染者の同居人、閉じられた空間の中で長く一緒に時間を過ごした者、適切な感染防護なしに感染者を介護した者、感染者の飛沫などに直接触れた可能性の高い者を「濃厚接触者」と定義した。1m以内の距離で互いにマスクなしで会話を交わした場合は、時間の長さを問わずに濃厚接触者に該当する場合があり、手で触れることのできる距離で、感染予防策が十分でないまま感染者と15分以上の接触があった場合も該当する。感染研が調査を行っていた時には、感染者の周りに調査をかけて濃厚接触者を特定していくが、実際は濃厚接触者でも言いたくないということが日本だけでなく世界中で起こっているため、大きく調査の網を掛け、聞き取りだけでは発見できないような濃厚接触者も一挙に検査対象に含めた。
最近は、高齢者や基礎疾患を持つ人の早期検出と隔離が重要になり、ワクチン接種が十分できていない方々は重症化のリスクが高いので、ワクチン未接種者の早期検出にもこういう対応を取っている。濃厚接触者をある程度決めて検査をしていく対応は今でも重要である。例えばある施設の感染管理を強化(=介入)すると、介入から14日間は感染者が出るかもしれないが、それ以降は感染者が出なくなり、少し過ぎたあたりで終息宣言となる。感染管理の専門家とともにこういった対応を取ることで、芯の通った感染対策ができる。
今はオミクロン株が流行する状況だが、オミクロン株流行前の段階で、世界の半数近くの人が1回は感染していると言われている。人類のかなり多くが感染してしまった中で、オミクロンになって患者が一気に倍ぐらいに増えた。世界には感染で免疫を獲得している人が多く、ワクチン接種で免疫を獲得している人が多い日本と他の国々で、感染状況の違いが生じる可能性がある。また、今はオミクロン株の中のBA.5が猛威を振るう中、私自身がこれまでリードしてきた積極的疫学調査において、濃厚接触者の特定や接触者調査はあまり行わなくてもいいだろうと言われている。ただ、オミクロン株は変異ウイルスとして出てきたうちの一つで、日本を含めて世界は数カ月ごとに新しい変異ウイルスを見ている状況であり、新たな変異ウイルスに対する備えを考え続ける必要がある。
3.FETPが全国的に取り組んできたクラスター対応の変化
新型コロナウイルス感染症の初期段階では、地域封じ込めや事例対応を目的に、疫学調査や感染管理、病院機能維持といったクラスター対策を行ってきた。それから、アルファ株の出現とともに、ゲノム情報と疫学情報を突合させて変異ウイルスを早く見つけ、その変異ウイルスが広がるのを少しでも遅らせる対応をとった。さらに、変異ウイルスの知見が随分異なるので、それぞれのウイルスの特徴を見つける作業(深掘調査)を行った。
クラスター対策の三つの柱=疫学調査、感染管理、病院機能維持のうち、感染管理と病院機能維持については自治体がかなり工夫をし、院内・施設内感染に関する関係機関との連携体制やDMAT(災害派遣医療チーム)の支援体制の強化が進んでいるが、疫学調査はやや時間がかかっている。クラスターの3分の2ほどは医療機関や高齢者施設で発生しており、専門家はその中で疫学調査や感染管理のアドバイス、病院施設機能維持に従事してきた。ところが2021年に入ると、医療機関や高齢者施設への派遣要請は急激に低下した。
感染研は、封じ込めを行う活動を続ける中でさまざまな事例に出会い、得られたキーワードを国民に情報還元した。最初は「クルーズ船」「スポーツジム」「デイサービス」「ライブハウス」「夜の街」「屋形船」「院内感染」「障害者施設」、時が進むと「調査へ非協力的」「休憩室」「標準予防策の不備」「歩き回る認知症高齢者」「ホストクラブ」「離島」が出てきて、最近「米軍基地」が出てくる。そうしたキーワードを情報還元するのが専門家の大きな役割だったが、変異ウイルスの時代になり、変異ウイルスを早く見つけて感染拡大を遅らせることに役割が変わった。
変異ウイルスが入ってきては自治体が止め、一つ一つのクラスターに自治体がしっかり対応することでウイルスの広がりを抑えていたが、その中で抑え切れなかったものが全国的な流行につながった。アルファ株に関しては、クラスターの連鎖を途中で止めることができた事例が大半だったので、多くが全国的な流行につながらなかった。デルタ株に関しても、大きな流行の起点になったものが七つあったが、そのうち六つについては自治体がそれぞれ封じ込めに成功した。いずれの事例にも感染研のメンバーが現場に参加していた。七つの事例は全てインドやネパールからの流入で、突破されてしまった1事例は実際に介入に入った時点でかなり拡大していて、手遅れの状況であった。
オミクロン株(BA.1)に関しても、幾つかの大きな波とウイルスの系統が入ってきており、ある系統は、日本国内各地の保健所が拡大を止めることに成功し、流行することなく終わった。オミクロン株の大流行には、沖縄県や山口県の米軍基地との関連もあっただろうと推測され、最初から大量のウイルスが入ってきて、とても対応できる状況ではなかったとみられている。水際対策をしっかり行い、ウイルスが少ない量で入ってきた場合には日本の保健所はかなり対応できることがわかった。
4.BA.5に関する情報提供
BA.5については、感染研として、それまでのBA.1などと比べて感染拡大抑制のための接触者調査を行える状況ではなく、十分な対応を行うことができていない。BA.5は南アフリカで最初に出現した可能性が高い。現在主に猛威を振るっているBA.5とその前のBA.4は、最初のBA.1、BA.2などと比べ伝播性が10%以上も高いと言われ、また中和活性の低下をもたらすことからワクチンの効果が十分ではないかもしれないとも言われている。しかし、どのようなウイルスに対しても、ワクチンをしっかり3回以上打つことは有効である。
日本では、第7波の感染拡大が西日本(島根県や九州北部など)から東へだんだん進んでいった。BA.2などの流行株がある程度抑えられていた西日本で、流行の速度が速いBA.5の置き換わりが早かった。BA.5については患者数の増え方が非常に早い。多くの方が感染してしまうので、重症者・死亡者の増加につながる怖れがある。また、それまで新型コロナウイルスは子どもには影響が少ないと言われていたが、今回は子どもの感染者が多く、重症になる子も出てくる恐れがある。日本の小児ワクチン接種率は高くないため、気をつけなければならない。インドではBA.2.75の感染報告数が増えており、これが次の第8波になるのではないかと警戒されている。
日本では、患者はたくさんいるにもかかわらず、感染拡大は終わっていると思っている方が多いが、変異ウイルスの出方を見ると、この1年間に2~3回の大きな波が起き、そのたびに感染者数も死亡者数も多くなっている。もう一つ気になるのは、新型コロナウイルスが野生動物に伝播しているという情報である。動物との接触が多い人や動物の肉を食べる人に感染していくリスクが懸念され、動物と人間のウイルスの連続性について警戒する体制が重要である。
5.今後も変異株への備えが必要
今後も変異ウイルスの出現への警戒や備えが必要な状況は続いている。経済活動も含めた通常の活動がなかなかできないのではないかと不安になるが、全体がロックダウンをして動きを止めるのではなく、対策の基本は自己防衛である。自分を守るために対策すること、それぞれの年齢や基礎疾患に応じてワクチンを接種すること、通常の感染対策-手洗いの徹底、適切なマスクの着用、三密の回避、こまめな換気など-は、今でも非常に重要である。特に食事中マスクを外して大声でしゃべることは慎んでいただきたい。ワクチン接種については、2回の接種では免疫の質も量も十分でないが、3回接種することで抗体が安定化する。感染すると後遺症が残ったり、は亡くなったりする恐れがあるので、必要な人は4回、小さい子どもから若い方も含めて3回は接種していただきたい。必要な感染対策を頑張って、個人防衛で乗り切りたい。
ヨーロッパの学術誌では、各国が罰則をもって個人の行動を変容しようとしたが困難だったこと、検査能力が最初は十分でなく、大量の検査がうまくいかなかったこと、日本がクラスター対策として取り組んだ接触者調査は非常に重要であることが指摘されている。日本の保健師たちはこの対応で電話をかけたり、話を聞きに行ったりしているが、世界のほとんどの国が、患者数の著しい増加により濃厚接触者を特定して行う接触者調査をやめている。さらに、自宅隔離と言いながら、食料の手配などの問題が解決されていないこと、予防接種をしっかり行うことで対策を終えた国が多いがそれで終了ではないということが指摘されている。個人の予防策としての手洗いやマスクの適切な着用、三密の回避、換気及びワクチン接種が必要な状況は、世界中で変わらない。
6.クラスター対策の今後
新興感染症がはやって、感染者が増え切ってしまうと役には立たないが、少しずつ増える時期にはクラスター対策は有効であると期待された。ワクチンが登場して、これを接種することで患者の発生がぐっと減り、その間少しずつ感染者が出た時にクラスター対策を頑張れば流行は抑えられるだろうと。ところが、残念ながら大きなウエーブがひっきりなしに続いている。クラスター対策が有効である時期は限られていて、感染者が増える時期にはあまり有効ではないと言える。ただ、家庭内感染が半分以上を占めることは変わらないので、クラスター対策としての接触者の追跡は流行が拡大し始める時期に限って行う、増えた時期でも陽性者に対して家庭内感染を防ぐ工夫をするようにお願いすることは有効で継続すべきと思われる。今後重症者がもっと出てくるようなウイルスに対する備えとして、オン・オフの体制を整えることが重要である。
オミクロン対策として、個別の医療機関や高齢者施設等では依然として積極的疫学調査が必要である。政策として「クラスター対策のオン・オフ」(流行に向かう時はオン、流行拡大期が過ぎたらオフ)をつけ、変異ウイルス発生時には、起点のゲノム情報を収集・分析・発信する。そうした政策推進の理論的な裏付けを、感染研が担う。
とかく人々は楽観的な方向のみを考えてしまいがちだが、いろいろなウイルス変異の可能性を考える必要がある。その中でどんな対応を取ることを人々が納得できる最善の道とするか、明確な目標を掲げ、その目標に応じて接触者調査やいろいろな戦略を整えることが大事である。これからの目標設定のために、専門家と国民がディスカッションをしっかり行い、合意形成していく必要がある。専門家は、靴の底がめくれるまで一生懸命いろいろな自治体の現場を歩き、協議し、実際に悲しい場面にも遭遇しながら対応してきた。今後も活動を続けていくためには、国民の公衆衛生活動に対する理解が必要不可欠である。
- ◇記念講演3「激動の世界とアジア経済の行方」 概要
- 澤田 康幸(東京大学大学院経済学研究科教授/前アジア開発銀行チーフエコノミスト)
世界とアジア経済について、過去50年の成功、現在の新型コロナウイルス感染症の影響、今後のウクライナ戦争によるリスク、そして急速に進化したデジタル化等、アジア経済におけるポストコロナのニューノーマル(新たな常識の定着)という、歴史・現在・未来の三部構成で議論する。
1. アジア開発史:政策・市場・技術発展の50年
この50年で、世界経済に占めるアジア経済のシェアがかなり高まった。ADB(アジア開発銀行)が「アジアの途上国」と定義する46カ国・地域の世界経済に占めるシェアは、1960年の4%から2018年には24%に増えた。これに「アジア太平洋地域の先進国」(日本・オーストラリア・ニュージーランド)を加えると、1960年の13%から2018年には33%まで増え、今後もさらに増える見込みである。その結果、「アジアの途上国」の貧困人口比率は、1980年の7割程度から現在7%以下と劇的に減少している。
アジアの成功の主要因を、ADBは五つにまとめている。
①将来を見据えた政府のサポートによる市場機能の活用。
②産業構造の高度化。
③生産能力への投資(物的資本やインフラストラクチャー)や人的資本の構築(教育、健康など)。
④技術を海外から輸入・模倣する立場から、世界経済の技術革新を牽引する立場への変貌。
⑤日本を含む先進国やADB・世界銀行等の国際開発金融機関との有効なパートナーシップ関係の構築。
第二次世界大戦直後のアジアの政府主導の開発政策は、市場よりも政府主導の工業化政策が軸になっていたが、順繰りに市場メカニズム、市場志向の改革を各国が採用し、成長が強まった。特に何らかの危機が起こった際に、それをきっかけとして改革・開放、経済成長などの構造変化が起こるというパターンが見られた。中国にとっては文化大革命、インドにとっては湾岸戦争時における国際収支危機、東アジア・東南アジアにとってはアジア通貨危機、日本にとっては第二次世界大戦が、その後の経済成長を促した。阪神・淡路大震災からの復興が淡路会議始まりのきっかけとなったように、危機や災害は大きな改革や新しい動きの契機になっている。従って、現在のコロナ禍やウクライナ戦争が契機となって改革が進む可能性があるということも過去50年の歴史から示唆される。
農業主体から製造業へ、さらにサービス業へと産業構造が順調に変化したこともアジアの経済成長の源である。先進国も同様の構造変化を経たものの、変化のスピードが非常に速かったこと、農業・製造業・サービス業それぞれのセクター内での生産性が継続して伸びたことで国全体の生産性が継続して向上したことがアジアの特徴である。
アジアは、まず先進国から技術を輸入・模倣した。留学、技術者の海外派遣、日本も積極的に行った技術ライセンスの輸入、リバースエンジニアリングなどが進められ、積極的に貿易や設備投資を行った。そこから、自ら技術革新・イノベーションを起こす方向に向かっていった。アメリカでの特許承認数について、1965~69年はドイツ、イギリス、フランス、日本、カナダがトップ5で、アジアからは日本だけがランクインしていたところ、2015年は日本が1位で、韓国、ドイツ、台湾、中国とトップ5のうちアジアの国が4つランクインした。インドもトップ10に入っており、アジアがまさに世界全体の技術革新を担っている。
近年まで、日本がトップランナーとしてよりハイテクノロジー製品や財を生産し、韓国や台湾、香港、シンガポールが日本の後を追い、その後を東南アジア・南アジアの国々が追う雁行形態型での「産業間の貿易」を通じた経済発展が進んできた。一方、技術水準があまり変わらない財をアジアの国々が作り、持ち寄って中国でiPhoneを組み立てるような、サプライチェーンネットワークやGVC(グローバルバリューチェーン)が最近は増えている。そのため、アジアにおける中間財の輸出割合は年々大きくなり、GVC、「産業内の貿易」へと軸足が動いている。
発展の初期において、こうした国際的なアジアの発展を支えたのが主に外国からの開発協力資金で、さまざまな分野においてアジア地域は二国間・多国間の経済協力、開発協力、資金協力を受け入れてきた。
2. アジアにおけるコロナ禍とウクライナ戦争
世界全体の新型コロナウイルス感染者数を見ると、2022年初頭から感染力の強いオミクロン株がパンデミックに大きな拍車をかけた。パンデミック収束は日本と同様、アジアでも途上だが、ワクチン接種率を欧米と比べると、2回接種の比率はアジアの途上国ではアメリカよりも高く、3回接種の比率は低い。コロナ禍は健康上、公衆衛生上の危機であるとともに、甚大な経済被害を生み出し、国内需要も観光需要も激減した。
こうした経済被害に対処するため、各国政府は大規模な財政金融政策を打ち出した。アジアの途上国全体の財政金融政策の規模は、GDP(国内総生産)の17%にも相当し、医療や生活サポート、ビジネス支援等、社会経済活動を維持するために使われた。
中国は上海のロックダウンを再発動するなど、移動制限を続けているが、その他の国はオミクロン株が流行していても、社会経済活動への制限は順次緩めている。その結果、2022年初頭のアジア経済は、景気も上向きになり、活発な状況を保っている。2020年3月のWHO(世界保健機関)によるパンデミック宣言以降、ほぼ100%休止されていた海外からの観光客の受け入れも徐々に緩和され、特にモルディブはパンデミック前の水準に戻っている。
アジア経済はコロナ禍から回復を進めているが、ロシアによるウクライナ侵攻が新たなリスク要因となってきており、エネルギー価格や農作物価格が世界的に上昇している。国別で見るとウクライナやロシアに近い中央アジアのインフレ率が高くなっているが、アジア全体としても今後インフレ率が上昇すると予想されている。
金融の動きは、2021年11月にアメリカのFRB(連邦準備制度理事会)が政策金利を上げる方向に舵を切ったことでドル高となり、アジアの対米ドル為替レートが減価した。FRBの政策がアナウンスされるたび、ロシアによるウクライナ侵攻があるたびに、株価も下落している。経済危機を抱えるスリランカ、債務問題を抱えるパキスタンでリスクプレミアムが高くなり、ウクライナ危機を受けて中央アジアでも急上昇している。一方、対外的ポートフォリオ資金(民間の短期資金)については、FRBの政策金利を上げる動きを受け、中国以外のアジアで短期資金が流出している。そうした金融情勢が弱まる傾向に対し、スリランカ、パキスタン、韓国を始め、各国は政策金利を上げ、金融引き締めの方向に動いている。
アジアの途上国全体の経済回復は、2022年は4.6%、2023年は5.2%の成長、特に東アジアは3.8%と4.5%、スリランカを除く南アジアは6.5%と7.1%、東南アジアも5%と5.2%と、堅調に上昇し、コロナ前の経済状態に戻りつつある。
3. ポストコロナのニューノーマル
ポストコロナでアジアが直面する課題、解決すべき問題を五つ挙げる。
①パンデミックとウクライナ危機という二つの危機の克服。また、将来起こるであろう危機・災害に対して強靭な社会経済を構築すること。
②コロナ禍で早まったデジタル化の潮流を止めず、むしろそれをてこにして技術革新による成長を進めていくこと。
③デジタル化による格差(デジタルデバイド)の是正と、気候変動対策等、健全なビルド・ベターによる持続的な復興・復旧の促進。
④少子高齢化等、急速な人口動態変化への対応。
⑤様々な課題を解決するためのリソース(資金)の手当て。
3-1. 災害に対応できる強靭な社会を構築
ウクライナ戦争には三つのシナリオが考えられる。
①原油価格が上昇し続けるだけで、社会経済にはあまり大きな影響が及ばない。
②原油価格が上昇するにつれて世界全体のインフレが加速する。
③急速なインフレが経済の悪化・停滞につながり、2008年のリーマンショックのような世界的金融危機が起こる。
GDP成長率はシナリオ①→②→③となるにつれて悪影響が大きくなり、特に③では来年大きな経済の減速があり得る。また、いずれのシナリオも2022年からインフレが加速することが予想されている。ウクライナ戦争が生み出す悪影響は経済全体に及ぶ。
また災害の歴史を見ると、1960年から現在まで、アジアの途上国全体として自然災害や技術的災害(原発事故などを含む)が増加傾向で、洪水や台風が頻発している。さらに自然災害の被災者の85%、死亡者の65%をアジアが占めている。人口急増や都市化により、災害リスクが高まってきていると考えられる。
自然災害の被害額が増えているにもかかわらず、アジアの途上国において、災害被害に対する市場保険のカバー率は、10%以下と非常に低く、公的な事前・事後の枠組みが重要である。災害については、国際連合の防災会議を中心とした枠組みが世界的に進化し、特に日本は災害大国として枠組みづくりに積極的に関わっている。現在は、防災・減災を気候変動リスクの文脈と統合しながら進めており、SDGs(持続可能な開発目標)が合意され、パリ協定も採択された。これらのアクションにより人々の生活を守っていくことが重要である。
3-2. デジタル化・技術革新による成長を推進
コロナ禍直前には、世界のおよそ半分のデジタル市場をアジアが占めていた。しかし、パンデミックによる経済封鎖がもたらす制約を回避するため、世界的にデジタル化が急加速する中、B2C(Business to Consumer)ビジネスのデジタル率は、アジアで急激に上がった。プラットフォーム経済が急成長したインドネシアが一つの例である。デジタル化による全アジアの利益は年間約1.7兆ドルで、GDPを年間約6%押し上げると考えられる。年約6,500万人もの雇用がデジタル化によって生み出され、貿易も活性化が見込まれる。デジタル化は復興・復旧を支える大きな潜在力を持っている。
3-3. 社会的包摂・格差是正・気候変動対策による持続的成長
しかし、アジアの中小零細企業間など広く経済全体においてデジタルデバイドが拡大した。デジタルデバイドを含む経済格差の拡大傾向は、既にコロナ禍前から20年ぐらいのスパンで起こっていた。国内のみならず、国家間でもインフラが進んでいる国と進んでいない国、デジタルプラットフォーム化・ネットワーク対応化が進んでいる国と遅れている国の格差が大きな問題となっている。また、アジアにおける温室効果ガス排出率は世界最速で増え、GHG(温室効果ガス)の世界全体の排出量の半分をアジアが占める中、クリーンなエネルギーへの転換、サステナビリティの広い達成もアジア全体の大きな課題である。
3-4. 少子高齢化・急速な人口動態変化に対応
アジアは、過去の先進国よりも速いスピードで65歳以上人口比率が増え、世界最速で高齢化が進んでいる。65歳以上と15歳未満の人口比率が反転する転換点を日本は1997年に迎えたが、アジアは2051年に迎える。労働年齢人口が相対的に減る状況で、高齢者になっても元気に働いて経済に貢献するシルバーボーナスをアジア全体でサポートしていくことが重要になる。
日本では、高齢者の生活は自己資金と公的な仕組みによって支えられており、60代は家族から支えられるよりも他の家族を支えている傾向があるのが特徴的で、日本の高齢者は持続可能な生活が維持可能である。一方、他のアジア諸国では、韓国も含めて自己資金や公的資金がかなり薄く、家族の支えに頼らざるを得ず、高齢化社会の中で全ての人々の生活を持続可能な形で支えていくことが今後の大きな課題となる。日本の高齢化の経験から、アジアは学び教訓とすることができよう。
3-5. 資金ギャップの穴埋め
新型コロナウイルスからの復興・復旧、ビルド・ベター、SDGsの達成を考えると、かなりの資金が必要となる。コロナ禍前の推計であるが、クリーンエネルギーへの転換、貧困対策、教育・保健への投資、ICTや技術サポートを含めたインフラ支援、生物多様性の維持のために、アジア太平洋地域全体として年間1.5兆ドルが必要となると試算されていた。それにコロナ禍からの復興が加わるが、既に各国は巨額の支援を行っているため、公的資金には限界があると考えられる。そのため、グリーンボンド、ソーシャルボンドといった民間の資金を導入していく必要がある。ASEAN+3(ASEANと日本・中国・韓国)のソーシャルキャピタルマーケット、グリーンキャピタルマーケットは拡大しているが、日中韓が中心的な役割を果たしている。
まずは政府が、国際的に通用するグリーンファイナンス、ソーシャルファイナンスの投資基準を設定するとともに、通常の経済危機やサステナビリティのリスクも併せた統合的な制度構築を行う必要がある。全体として投資がより進むような市場環境整備とともに、政府自身が課税強化、国際的な租税協力により財政のスペースを広げ、政府としても必要な投資を行っていくことが求められる。
4. まとめ
アジア経済発展の50年は、基本的に政府が市場活動を活用し、支えてきた。積極的な改革等により、技術も模倣から革新へ転換を遂げた。
現在進行形のコロナ禍は、大きな経済被害を生み出したが、復興の兆しは着実に見られている。とはいえ、ウクライナ戦争という新たなリスクが発生し、金融市場もその悪影響を受けているため、日本を含むアジアの政府は、堅調な経済成長維持・経済復興のために適切な対処が求められる。
未来に向けて、ポストコロナの持続可能なニューノーマルが必要である。災害への強靭性、デジタル化の推進、社会的包摂、デジタルデバイドの最小化、気候変動対策や環境対策、高齢化への対応が不可欠である。
つまり、政府のみならず民間がインフラなどへの必要な投資を行い、その必要投資額のギャップを埋めながら、民間・政府・市民社会で連携し、ビルド・ベター、SDGsの達成に向かっていくことが望まれる。