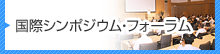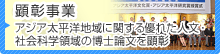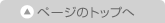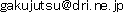第24回アジア太平洋研究賞佳作 受賞者 団 陽子氏
第24回アジア太平洋研究賞佳作 受賞者 団 陽子氏
論文タイトル「戦中戦後の国際関係における中華民国の対日賠償要求問題」

- 団 陽子氏
-
【略歴】
専門は、外交史、東アジア国際関係史。米国ペンシルベニア大学文理学部卒業。国内外勤務を経て、2014年、神戸大学博士課程前期課程博士課程前期課修了、中国浙江大学人文学院中国近現代史学科修了。日本学術振興会特別研究員(DC2)、日本学術振興会若手研究者海外挑戦プログラムの助成を受けて、米国メリーランド大学カレッジパーク校行動社会科学部客員研究員。2022年、神戸大学国際文化学研究科博士課程修了(博士(学術))。現在、東京大学にて日本学術振興会特別研究員(PD)、神戸大学、神戸学院大学非常勤講師。
【要旨】
-
中華民国の対日賠償請求問題に関する従来の研究では、米国の対日占領政策の転換を機に、米国の懲罰的な対日賠償政策が緩和から放棄へと変化したことで、中華民国の賠償要求は「挫折」を強いられたと論じられてきた。しかし、米国のハイレベル政策文書に基づくこれらの研究では、戦中戦後を通じた米華両政府の賠償政策の相違や連合国による賠償協議過程が充分に明らかにされておらず、米国の対日賠償政策の方向性がその当初より懲罰的であったのかどうかも検証されているとは言いがたい。そこで、本研究ではこれまで取上げられてこなかった米華両政府内や対日戦後処理機関である極東委員会(以下FEC)における協議過程に注目し、国際関係の視点から中華民国の対日賠償請求問題について実証的再考を試みた。その結果、次のことが明らかになった。
従来の見解では、戦後当初、米国政府は「中国大国化」を後押し、米華両政府ともに日本に懲罰的な賠償を求めていたとされるが、日本占領を主導する米国にとって賠償は占領管理における自国の利害に密接に関わる問題であり、その管理を阻害しかねない厳しい賠償を日本に課すことを米国は当初から望んでいなかった。また、賠償艦艇の分配において米国は、日本占領管理と安全保障上の懸念から最大被害国の中華民国よりソ連への対応を優先した。日本からより多くの賠償を求める中華民国と米国とは賠償問題において利害が対立しており、中華民国の賠償請求は米国の政策転換を待つまでもなくその当初から思惑通りには進んではいなかった。しかしながら、その制約下において中華民国政府は積極的に賠償獲得に努めた。FEC諸国の中で最も多くの日本の国内外資産を獲得した中華民国は、実際には当時の国際社会において賠償問題で「挫折」したとはみなされてはいなかった。
このように、「米国の政策転換による挫折」として定説化されてきた中華民国と日本の戦後賠償に関する問題は、長きにわたる冷戦やアジアの分断を経て、いまもなお冷戦観や関係国の政治的な評価が少なからず影響していると考えられよう。