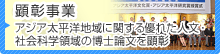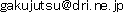第16回アジア太平洋研究賞(井植記念賞)受賞者 湯川 勇人氏
第16回アジア太平洋研究賞(井植記念賞)受賞者 湯川 勇人氏
論文タイトル「東アジア秩序をめぐる日米関係:1930 年代の外務省による東亜新秩序の模索」

- 湯川 勇人
-
【略歴】
専門は日本政治外交史。博士(政治学)。2013年3月、神戸大学大学院法学研究科博士前期課程修了。2013年9月から2014年6月までアイオワ大学客員研究員。2017年3月、神戸大学大学院法学研究科博士後期課程修了。現在、神戸大学大学院法学研究科特別研究員。
【要旨】
-
満州事変以降の外務省は重光葵や有田八郎ら「アジア派」がその中心であり、彼らが有していた、現行の国際秩序を打破し、新たな東アジア新秩序を建設するという対外構想は、現状を望む英米諸国との関係悪化の一要因であったとされている。しかし、このことは「アジア派」外務官僚たちが、対英米関係を等閑視していたことを直ちに意味するわけではない。「アジア派」外務官僚たちも、対英米関係の重要性を認識していたことは、先行研究において明らかにされている。つまり、1930年代の外務省は、新秩序建設と対英米関係維持という矛盾する2つの対外構想を同時に追求しなければならなかったのである。いかにしてこの2つの対外構想を両立しようとしたのであろうか。この問いに答えることで、1930年代の外務省の果たした役割を明らかにすることが、本論文の目的である。
そこで、本稿では「アジア派」の中心人物である重光や有田がなぜ国際秩序の打破を指向するに至ったのか、国際秩序の打破、新秩序の建設過程において、対米関係をいかに位置づけ、他方で米国はそれらをいかに認識していたのかを、当時の東アジア秩序の根幹であった九カ国条約や対中政策に関する対米折衝過程から分析した。また、満州事変以降、傍流となった「英米派」である佐藤尚武の対外構想や、第三極であった「革新派」外務官僚の対外構想を、「アジア派」の対外構想と比較しながら検討することで、特定の人物、集団だけではなく、1930年代の外務省を横断的に把握することを試みた。
その結果、当該期の外務省は、軍部の政治的発言権が増す中で、九カ国条約の運用意図を明確化することで、軍部の無統制な対中進出構想を外交で規定し、対米関係を維持しつつ、東アジア新秩序建設を達成しようとしたこと、他方で、勢力圏外交を展開した外務省は、最後までアメリカの唱える新外交が持つ理想主義との対立を解消することができず、挫折したことが明らかとなった。