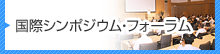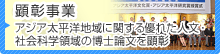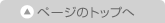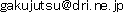第21回アジア太平洋研究賞 受賞者 大谷 亨氏
第21回アジア太平洋研究賞 受賞者 大谷 亨氏
論文タイトル「無常鬼の研究──〈精怪〉から〈神〉への軌跡」

- 大谷 亨
-
【略歴】
1989年、札幌生まれ。専門は中国民俗学。博士(学術)。2012年、中央大学文学部中国言語文化専攻、卒業。2014年、東北大学大学院国際文化研究科アジア文化論講座、博士前期課程修了。2015年-2017年、日本学術振興会特別研究員(DC2)。2017年-2020年、廈門大学人文学院に高級進修生として留学。2022年、東北大学大学院国際文化研究科アジア文化論講座、博士後期課程修了。現在、東北大学大学院国際文化研究科フェロー。
【要旨】
-
小論の目的は、中国学に「妖怪学」という研究分野を定着させることにある。その前提には、中国に息づく豊かな妖怪資源(例えば、妖怪伝承など)が、いまだ有効活用されていないという現状認識がある。私は、その等閑視されてきた資源を活用し、妖怪学を実践することで、従来の中国文化論が更新可能であることを示そうとしたのだった。
上記の背景のもと、小論ではアメリカの人類学者らが提起した「〈神(ゴッド)〉〈鬼(ゴースト)〉〈祖先(アンセスター)〉」という分析枠組み、及びそこから派生した「〈鬼〉から〈神〉へ」というテーマを批判対象として議論を進めることとした。これらの先行研究では、〈鬼〉の概念がもっぱら人由来の〈孤魂野鬼(=幽霊)〉として矮小化され、人を由来としない〈精怪(=妖怪)〉の存在が等閑視されていた。そこで小論では、〈精怪〉が〈神〉へと変容する事例を調査し、中国の民間信仰における〈精怪〉の位相を探ることとした。
上記の問題意識のもと、小論は無常鬼(むじょうき)という拘魂使者(澤田瑞穂は「死神」と呼んだ)を研究対象とした。なぜなら、くだんの無常鬼には、「〈精怪〉から〈神〉へ」の軌跡を辿った痕跡が散見されたからである。この仮説は、無常鬼をめぐる通説とは一線を画すものであったが、無常鬼の変遷史は未だかつて詳しく調査されたことがなかったのである。
小論では、無常鬼について記された文献資料を博捜するとともに、今日共時的に並存する多様な無常鬼イメージ(廟の塑像であったり民間伝承であったり)をフィールドワークし、その変遷史を浮上させようとした。
結果、無常鬼とは、山魈(サンショウ)や摸壁鬼(モヘキキ)(という〈精怪〉ども)に淵源をもつ、言わば「精怪的拘魂使者」であることが明らかとなった。さらに、その精怪性を漂白させながら、今日広く知られる〈神〉としての無常鬼イメージが形成されるまでの過程も明らかにすることができた。
上記の試みは、少なからぬ課題を残しながらも、中国妖怪学の方法論や可能性を具体的に提示する、今後の展開にとっても重要な論考になったと自負している。