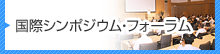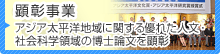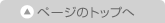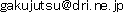第23回アジア太平洋研究賞 受賞者 温 秋穎氏
第23回アジア太平洋研究賞 受賞者 温 秋穎氏
論文タイトル「〈声〉の中国語受容の文化史研究―もう一つの教養語をもとめた近代日本」

- 温 秋穎氏
-
【略歴】
専門は人文社会情報学、中国語中国文学。2018年武漢大学新聞与伝播学院卒業、2021年京都大学大学院教育学研究科修士課程修了、日本学術振興会特別研究員DC1、国際日本文化研究センター特別共同利用研究員を経て、2024年京都大学大学院教育学研究科博士後期課程修了、博士(教育学)。現在、大谷大学国際学部助教。
【要旨】
-
中国語は外国語のはずであるが、近代における入り組んだ日中関係ゆえに、そして漢字を使って表記される性格ゆえに、その言語の「他者性」は常に曖昧かつ複雑なものであった。本論文「〈声〉の中国語受容の文化史研究―もう一つの教養語をもとめた近代日本」では、漢文訓読とは異なる外国語としての「〈声〉の中国語」が、近現代日本でいかに受容されてきたのかという課題を、文化史の手法で解明するものである。特に、1930年代から1960年代にかけて、ラジオや出版物といったメディアを介した日本国内の中国語学習の場において、中国語という外国語を「教養語」として追求した教育者と学習者の言動を考察し、これらの言動と思考の連鎖が当時の日本の中国認識、日中交渉にもたらした意味を検討した。時期設定の起点となる1930年代は、新しい音声メディアが出現し流行し始め、それに伴い中国語の流通状況が変えられたという〈声〉の中国語受容にとっての大きな転換点である。そして、時期設定の終わりは、日中双方の言語的近代がほぼ完成し、日本の中国語教育史のなかの倉石武四郎の時代が終わった1960年代後半とする。
具体的には、第1章から第4章までは1930年代前後から敗戦までの時期を取り扱い、日本放送協会が1931年から1941年にかけて放送したラジオ「支那語講座」や、その同時期に形成された発音記号による「耳の拡張」としてのテキスト空間、独習者に向けて発行された学習誌、さらに中国語教育の改革を志した岩村成允と倉石武四郎らの思想的動向などを分析対象とした。一方、第5章から終章では、アジア太平洋戦争の敗戦という近代の中国語受容の転換点を経た、戦後の状況を中心として考察しており、新制東京大学における中国語を必修とする「Eクラス」の誕生や、その同時期に再開されたラジオ講座をめぐる動きなどを論じている。