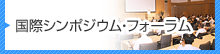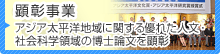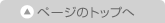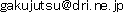第24回アジア太平洋研究賞 受賞者 ザヘラ モハッラミプール氏
第24回アジア太平洋研究賞 受賞者 ザヘラ モハッラミプール氏
論文タイトル「20 世紀初頭の日本における「東洋」概念の拡張 ――伊東忠太とその周辺の建築家・美術史家・歴史学者たちのペルシア観を中心に」
- ザヘラ モハッラミプール氏
-
【略歴】
専門は比較文学・比較文化。2014年より日本に留学。2023年、東京大学大学院総合文化研究科超越文化科学専攻比較文学比較文化コースにて博士号(学術)取得。日本学術振興会外国人特別研究員(国立民族学博物館)などを経て、現在国際日本文化研究センター上廣国際日本学研究部門特任助教。著書に『「東洋」の変貌――近代日本の美術史像とペルシア』(名古屋大学出版会、2025年)など。
【要旨】
-
現在、東京国立博物館の東洋館内にある常設展示室には、「西アジア・エジプトの美術」というコーナーがある。この展示室に足を運ぶ現代の日本人は、これらの地域の美術が「東洋」という枠組みに入れられたことを疑問に思うことはないかもしれない。しかし、20世紀初頭の「東洋美術」で扱われる範囲は、日本、中国とインドであった。そうであるならば、西アジアとエジプトの美術を「東洋」に含めるという認識の基盤はいつ、どのようにして形成されたのであろうか。
この問いに一つの答えを与えるために、本論文は、建築家・建築史家の伊東忠太(1867-1954)を中心とした20世紀初頭の建築・美術界におけるペルシア美術の受容と「東洋」観に着目する。具体的には、古社寺が所蔵する宝物の調査が行われ、法隆寺に所蔵されるテキスタイル「四騎獅子狩文錦」の起源がサーサーン朝ペルシアにあったことが議論された1890年代から、東京帝室博物館の関東大震災からの復興活動の中で「東洋」の範囲が「ペルシヤの辺」までと拡張された1929年までを扱う。この時期の言説を分析することを通して、日本におけるサーサーン朝の芸術の捉え方が、ペルシア美術全体のイメージ形成に影響を与え、「東洋」という概念が西アジアにまで拡張される一因になったことを明らかにする。
とりわけ、本論文では1893年に「法隆寺建築論」を発表した後の伊東の活動を中心に追いながら、彼と交流の深かった歴史学者の黒板勝美(1874-1946)のペルシア旅行や当時の美術商についても取り上げる。彼らが関わった美術出版、展覧会、講演会等を跡付けながら、「東洋美術史」が構築される過程を浮き彫りにする。
日本における「東洋美術史」は、日本美術の源流として認められたアジアの美術から構成される。20世紀初頭において、ペルシア美術は、四騎獅子狩文錦の文様の起源として国際的に認められたことに加えて、西アジアにおける美術の集大成として認識された。それゆえペルシア美術は、東京帝室博物館の復興活動の流れの中で、「東洋」概念が西アジアにまで拡張される鍵となったのである。