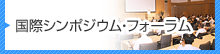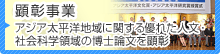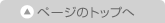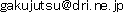第24回アジア太平洋研究賞佳作 受賞者 西浦 まどか氏
第24回アジア太平洋研究賞佳作 受賞者 西浦 まどか氏
論文タイトル「手話を聞く-バリ島ブンカラ村における「聾であること」と〈身体のポエティクス〉」

- 西浦 まどか氏
-
【略歴】
専門は文化人類学(音楽人類学・言語人類学)。博士(学術)。2016年に東京藝術大学音楽学部(音楽学)を卒業。最終年度に安宅賞受賞。2018年-2021年に日本学術振興会特別研究員(DC1)、2021年-2022年・2023年-2024年にハーバード大学客員研究員を経て、2024年に東京大学大学院総合文化研究科の修士課程・博士課程(文化人類学)を修了。現在、東京大学総合文化研究科学術研究員、法政大学人間環境学部・聖心女子大学人間関係学部・玉川大学リベラルアーツ学部にて非常勤講師。
【要旨】
-
本論文は、聾者の出生率が高いことで知られるインドネシアのバリ島北部にあるブンカラ村を対象とした、聾と手話に関する文化人類学的な民族誌である。
本論文は3つの部からなる。まず第Ⅰ部では、先行研究のレビューを行い、本論文の理論枠組みとして〈身体のポエティクス〉という独自の理論枠組みを提示した。次に第Ⅱ部では、ブンカラにおける「聾者性」の社会文化的な位置づけを、ローカルとグローバルの両方の観点から民族誌的に描き出した。そして第Ⅲ部では、現地でうまれたカタ・コロッ手話コミュニケーションでの語り方の工夫とその社会文化的な効果について、細かい事例分析を通して探究した。
本論文は以下の3つの学術的・社会的貢献を目指したものである。第一に、本論文は「遺伝的に聾者が多い」という特殊な状況であるブンカラ村での、おそらく初の本格的な長期調査に基づく民族誌である。とくに第Ⅱ部では、村に聾者が多い理由、聾者コミュニティのあり方、村の慣習村法で定められた墓堀などの聾者の役割など、村における「聾であること」の多層性を描き出した。
第二に、コミュニケーション研究への貢献である。本論文では新たな理論的視座として〈身体のポエティクス〉を提示し、第Ⅲ部にて実際のブンカラ村での手話コミュニケーションにおける社会政治的な効果を詳細に分析した。この視座は、世界各地の様々な手話言語、そして音声言語コミュニケーションにおける身体性の側面やダンスなどの身体表現などにも拡張しうる可能性をもつだろう。
第三に、他者と向き合う倫理の問題を発信した。本論文ではブンカラ村における「聾であること」の位置づけにおいても、〈身体のポエティクス〉の効果においても、聞き手・受け手の側の倫理的態度が重要であることが明らかになった。コミュニケーションの態度と倫理の問題として「手話を聞く」ことの重要性とやり方を問いかけることが、本論文の隠れた目的であり、おそらく最も重大な貢献であるものである。