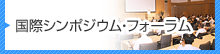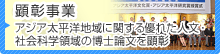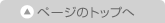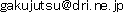第8回井植記念「アジア太平洋研究賞」 受賞者:李 東俊(り どんじゅん)氏 論文要旨
第8回井植記念「アジア太平洋研究賞」 受賞者:李 東俊(り どんじゅん)氏 論文要旨

- 李 東俊(り どんじゅん)
- 【経歴】
1994年韓国ソウル大学人文学部卒業。1993年11月から2005年3月まで「韓国日報」政治部記者(外交・統一問題取材)。この間、韓国カトリック大学国際大学院修士課程(朝鮮問題専攻)修了および日本国際交流基金招聘研究員(東北大学法学部客員研究員、1年間)歴任。2008年9月東北大学大学院法学研究科博士後期課程修了および博士号取得(法学)。2009年より日本学術振興会外国人特別研究員(中京大学外国人客員研究員)。最近は、近年秘密解除された日韓国交正常化交渉に関する外交文書を用いて日韓関係の歴史的展開を分析することに研究の重点を置いている。
冷戦の終焉から20年以上も過ぎたものの、朝鮮半島をめぐる緊張状態は解消されないばかりか、むしろ北朝鮮の核開発を契機にして高まっている。まさにポスト冷戦時代なのに、なぜ朝鮮半島は「冷戦の孤島」のように変わらないのか。本稿は、この質問に対する一つの手がかりを、冷戦史において一般に「デタント期」として知られる1970年代前半における米中和解と、それに伴った朝鮮半島分断構造の変容から探ろうとする。この時期の米中関係については、従来主として台湾問題を中心とした二国間関係や米中ソ日など大国間の勢力構造の脈絡で説明されることが多かったがゆえに、その朝鮮半島との関連性はあまり注目されなかった。しかし本稿では、この時期における米中和解と南北対話という二つの緊張緩和の相互作用の結果、朝鮮戦争以来の対立構造が再編され、分断構造の性格をも一変し、その基本属性が今も維持されている、という視座を示す。 米中和解と朝鮮半島問題との相互関係を分析する上で、本稿は、分断構造に内在する二つの対決要因に注目する。その一つは、朝鮮半島における唯一合法政府という意味での「正統性」をめぐる問題である。米中和解と中国の国連復帰(中国と国連との和解)を機に、朝鮮戦争の際に中国とともに国連から「敵性団体」と規定された北朝鮮の法的・政治的地位の正常化問題が問われた。その際、それまで朝鮮半島における「唯一合法性」を韓国だけに与える根拠となっていた所謂「国連帽子」、即ち国連の朝鮮半島問題への政治的かつ軍事的介入をそれぞれ象徴する国連韓国統一復興委員会(UNCURK)と国連軍司令部(UNC)の解体問題が焦眉の課題となった。もう一つは、在韓米軍に象徴される「安全保障」をめぐる争点である。在韓米軍の駐留とその位置付けに対する共通了解は、米中和解における前提条件であったからである。米国は、少なくとも在韓米軍が中国を標的としていないことを中国に理解させる必要があったが、南北双方にとってそれは各々の国家安保に関わる重大問題であった。
こうした二つの争点をめぐる関連諸国間のせめぎ合いは、朝鮮半島をめぐるデタントの方向性を左右し、朝鮮半島分断構造を不断に再定義しながら展開した。第1章では、予備的考察として、上記争点と、米中対決が南北対決を後押しする「入れ子的」対決構造を特徴とする分断構造との関連性について検討した。
第2章では、米中「接近」期とも言える69年から70年までにおける、米中関係と朝鮮半島情勢について考察した。その焦点は、ニクソン政権が従来の対中封じ込め政策の見直しとともに推し進めた在韓米軍撤収政策に当てられる。米国はそれまで中朝連合軍に対する抑止の手段として位置付けてきた在韓米軍を減らすことで、中国を安心させ対中接近の道を開く一方、対中接近によってアジアに対する軍事的コミットメントの縮小を骨子とするニクソン・ドクトリンを具現しようとした。その結果、在韓米軍第7師団が撤退し、また韓国軍が第2師団の作戦地域を接収することで、朝鮮戦争以来初めて軍事境界線は南北間の対峙線に局地化した。これは軍事的対峙を続けてきた南北関係の変化を促す物理的基盤となった。
そして71年以来主としてキッシンジャー訪中を通じて展開した米中「和解」の場では、両国の戦略的利益に適うように朝鮮半島に対して「共同の影響力」を行使する必要性が訴えられる中、朝鮮半島問題をめぐる取引が本格化する。こうした米中による「上からのデタント」を受けて南北双方は、後ろ盾の同盟大国から見捨てられかねない危機意識を共有しつつ、「対話」に踏み切る一方、それによる国内体制のリスクをヘッジする方法としてそれぞれ前代未聞の権威主義体制を立ち上げた。第3・4章で示すように、南北関係は米中和解の「ショック」を吸収する形で、それまでの「対話なき対決」から「対話ある対決」に移りつつあった。
第5章では、米中が73年にソ連への共同対抗を目的とする「戦略関係」を構築した上で、朝鮮半島問題に対して合意点を見出す経緯を検証した。まず米中は在韓米軍に関して、大国間関係と朝鮮半島情勢の「安定」に鑑み、その「段階的撤収」に接点を求めた。こうして中朝連合軍に対する抑止力として機能した在韓米軍は、朝鮮半島及び周辺地域の「安定力」(stabilizer)として蘇った。更に米中は、国連に関わる正統性争点においても協力し、UNCURKが第28回国連総会で「静かに」解体された。要するに、米中が追求した朝鮮半島問題解決の方向性とは、分断構造の解体、即ち統一ではなく、朝鮮半島における正統性と安全保障をめぐる競争の均衡化と、米中共同の介入を前提にする分断構造の安定化に他ならなかった。
ところが、こうした米中の「取り決め」は、同盟間及び南北間にデタント観と安全保障観のズレを引き起していた。第6章で示すように、北朝鮮は74年、韓国の当事者能力を否定した上で、朝鮮戦争の戦後処理の方法として米朝平和協定の締結を要求するが、それに対して米中両国は「共同の影響力」行使よりも同盟利益を優先する。結局、74年と75年の国連総会において、米中はそれぞれのジュニア・パートナーと手を組んで真正面から対決し、その結果、相対峙する両側の決議案が同時に採択される「異変」が生じた。
にもかかわらず、この時期における「米韓対中朝」の対立軸は、米中接近以前とは本質的に異なるものであった。米中両国は朝鮮半島問題をめぐって表向きには反対の立場に立ったものの、他方で秘密交渉への努力を払いつつ、在韓米軍の「安定力」としての役割について了解し合い、あまつさえ最大の争点であった国連軍司令部解体問題をめぐっても停戦体制の維持という戦略的利益を共有していたからである。75年の国連総会における両決議の成立も結果的に、朝鮮半島における二つの敵対的な合法政府の承認と、在韓米軍問題の事実上の永久凍結を生み出したという意味で、米中「妥協」の産物であったと言える。
それらは、米中間の適当な牽制と協力を内容とする「朝鮮半島をめぐる米中協調体制」(U.S. and China Concert of Korean Peninsula)とも言うべき新しい危機管理システムの成立を裏付けており、朝鮮半島問題が米中の戦略的利益の枠内で統制され続けることを意味した。こうした構造的変化を受けて、それまで相手の存在すら否定する「敵対的対決」に没頭してきた南北双方は、「二つの韓国」の「共存」を所与の条件として受け入れた上で、相手への現実的な対応として体制間競争を展開した。デタント期において、米中和解と南北対話、米中「裏」交渉という「三つのドラマ」を通じて再編された朝鮮半島分断構造は冷戦終結後、新たな不安定要因を内在しながらも、その基本骨格を維持し続けているのである。