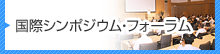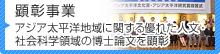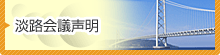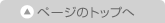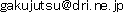淡路会議声明 2004
淡路会議声明 2004
2004年8月7日(土) 第5回アジア太平洋フォーラム・淡路会議
安全保障とはさまざまな脅威や危険から人々の生命(いのち)と生活(くらし)を守ることを意味する。安全保障は多面的・総合的である。北朝鮮の核とミサイルが日本に向けられるという国家レベルの脅威、テロリストによる日本攻撃という新しい脅威、イラクに続いてサウジが混乱に陥るような場合に生ずるエネルギーと経済の危機、大地震や集中豪雨などの自然災害、こうしたさまざまな分野からの危険がひとしく人々の生存を脅かしうる。阪神・淡路大震災10周年を前に開催された第5回淡路会議は、21世紀を迎えた日本とアジア太平洋地域の安全保障を2日間にわたって検討し、その成果を次の4つのレベルにわたって声明する。 1.外交安全保障、 2.経済安全保障、 3.災害・防災を中心とする国内安全保障、 4.文化交流と多様な価値の共存・共生、の四分野である。
【外交安全保障】北朝鮮問題は第二次大戦と冷戦の後、今日まで東アジアに残された安全保障上の重大問題である。6者協議と2国間交渉の併用により、地域的な安定のため不可欠な朝鮮半島の非核化をなしとげ、最終的に地域の経済相互依存の中に北朝鮮を組み入れることを外交的に成し遂げねばならない。戦後の世界的変化にとり残されたように見える北朝鮮社会であるが、すでに経済面、情報面でも孤立した存在ではありえなくなっている。たとえば、脱北者の多くがラジオで外国放送を聞いていたと証言している。こうした北朝鮮の変化がさらに進展し、軍事的暴発を抑えつつ内部変化が進行することが望まれよう。4半世紀前に鄧小平のリーダーシップのもとで経済発展を軌道に乗せた巨大な中国の興隆は、21世紀の世界における主要問題であり続けるであろう。20世紀におけるドイツや日本もそうであったように、新勢力の勃興は歴史上しばしば戦乱を招来してきたことを忘れるべきではない。中国にも沿岸部と地方とのギャップ、環境問題や政治的腐敗、台湾海峡の対立などの問題が現存する。こうした問題をはらみながらも、今日の中国は6者協議をリードし、ASEANとの自由貿易協定を約し、南シナ海の領土問題で柔軟姿勢に転ずるなど、マルチの枠組みを重視し信頼醸成に努める外交戦略をとっている。こうした新たな積極的行動主義によって、中国は東アジア国際政治の中心的存在となってきたが、古来の「中華秩序」の回復に向かうのではなく、中国が国際システムのなかで責任ある役割を果たし続けることが必要である。ASEANの発展は東南アジア地域の安定だけでなく、APECの運営の中心をつとめ、ARF(ASEAN Regional Forum)という安全保障のひさしを拡げ、さらに東北アジアの日中韓3カ国の集りの場を提供するなど大きな役割を果たしてきた。日本は東南アジアのこうした進展を支持してきたが、今後ともアジアにおける「諸国民の自由」が保持される東アジア共同体の形成をリードすべきである。冷戦終結後の日本はさまざまな危機や試練にさらされる中、歩一歩外交安全保障面の役割を拡大する対応を重ねてきた。こうした漸進的な変化は評価されるが、日本にもあらたな時代の要請に応えることのできる力強いリーダーの登場が望まれる。日本は自国の安全保障のみならず、人間の尊厳と文化の多様性の尊重に立脚しつつ国際的な平和構築に力強い役割を担うべきである。この秋の大領領選挙の結果如何にかかわらず、健全な日米関係を維持発展させるため、知的準備と人的ネットワークの拡大が必要である。同時に、不安定要因をはらみつつも世界の中で比重が増している東アジアにおいて、建設的な協力関係を育て、あらたな共同体の建設に向かって日本が踏み出すことがきわめて肝要である。
【経済安全保障】東アジアにおける経済の相互依存関係は、1997年の金融・経済危機を越えて、さらに強化されている。中国は1980年からの持続的高度成長により、「世界の工場」といわれるにいたったが、それ以上に今や「世界の巨大市場」となっている。もちろん中国経済にも40%にのぼるとされる不良債権とバブル経済破綻の危険、電力不足、環境破壊、国内金融制度の未成熟など憂慮される陰の部分もある。しかし、東アジアの相互依存関係をより高度に多層的にしているのも、中国が資本財や高度技術を他国から輸入しつつ製品を世界に輸出する加工貿易の大拡張を行った結果である。相互依存の進展が、東アジアにいわば「運命共同体」的な関係を事実としてはぐくんでいる。急速な不均等発展を強行する中国が抱えるエネルギー問題や環境問題等について、日本は自らと地域全体の安全のため、その軽減のため積極的に協力すべきである。そして中国の強大な経済活力を、関西経済と日本経済に活かすことが重要である。
【防災・国内安全保障】今日のアジア太平洋には世界的に見て大きな災害が集中している。それには、太平洋海水の温度上昇に伴う台風発生の北上や集中豪雨、環太平洋地域における地震・火山噴火の多発など自然的要因と、都市化が社会インフラの未成熟なまま進展するなどの社会的要因とが複合して存在する。留意すべきは、公害と災害が連動しており、環境保全と防災とが不可分な関連を有するという事実である。いつ来るか分からない災害に備えることに懐疑的になるのではなく、日頃から人間を大事にし環境を守る強い社会をあらかじめ築くことによって事前防災体制を強化することが必要である。防災の担い手として行政に劣らず市民ひとりひとりが重要であることは阪神・淡路大震災の経験から明らかになった教訓である。たとえば多くの家屋が倒壊した北淡町に犠牲者がなかったのは、近所の人たちが互いのことをよく知り合うコミュニティが存在したからであった。「自助1割 公助7割」の通念を逆転させ、「自助7割」を奉じて個人と地域に防災情報を届けることが求められる。さらに進んで、兵庫には13の防災拠点がすでに存在するが、これを束ねて、この地が「国際防災」のハブとしての役割を担うべきである。日本は情報という財産を発信することにもっと大胆にならねばならない。
【文化交流と多様な価値の共存・共生】文化の多様性を認め、価値の差異を相互に尊重し、相互信頼をはぐくみつつアジア太平洋におけるネットワークを構築することが、今や喫緊の課題である。異なる文化の間で、個人、集団、国家の各レベルにおいて、相互理解を進め、他文化を学ぶことにより自らの文化を豊かにし、共同で問題に対処することができるよう対話と交流を促進することが望まれる。今日の世界には「文明の衝突」が危惧される事態が存在する。自らの価値とシステムへの絶対的信念のあまり、異質な文明を断罪し、力による解決に突き進む傾向は厳しく戒めねばならない。とりわけ先進社会は、文明間の対話、社会正義の重視、民主化などを通じて、不均衡をはらみつつ苦難に満ちた発展をとげようとする社会の中に政治的穏健路線をはぐくみ定着させる努力を重ねねばならないであろう。危機に満ちた21世紀初期の「海図なき航海」が、時が過ぎてみれば、よき努力のなされた時代であったと回想されるよう、われわれの英知を傾けてアジア太平洋におけるコミュニティ・ビルディングに力を合わせたいと思う。