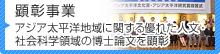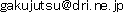淡路会議声明 2011
淡路会議声明 2011
2011年8月6日(土) 第12回アジア太平洋フォーラム・淡路会議
第12回アジア太平洋フォーラム・淡路会議は、2011年8月5日、6日の両日、淡路夢舞台を会場に、「21世紀再生戦略-安全・安心にして活力のある日本社会の実現に向けて-」をメインテーマとして開催され、活発な報告と討論が行われた。
3月11日の東日本大震災の勃発によって、当初から予定していた高齢化社会の福祉・産業・文化の問題に加えて、震災対処や復興の問題が大きくクローズアップされ、いわば二本立ての熱い討論を繰り拡げた。
日本の歴史は、国難をばねに大躍進を遂げてきた。大和王朝が663年に、唐・新羅に滅ぼされた友好国の百済を救うために2万8千人の大軍を朝鮮半島に差し向け、完敗した。それは大変な衝撃で、唐・新羅の連合軍が攻め込んでくるだろうという危機感の中、大和王朝は防人を東北から九州、対馬地方に配備し、たくさんの城を造り、のろしという通信システムまで整備し、むしろその危機感の中で統一国家らしい国内体制を作り上げた。
しかし、それよりも大事なことは、敗戦の翌年から猛然と唐文明を学んだことである。負けて、唐の文明がいかに優れたものか思い知った。当時はローマ帝国崩壊後であり、世界で一番水準の高い文明は唐だった。その唐から50年間学んで、710年に唐の律令国家の都のミニチュアである平城京を奈良盆地に作ったのである。そのことは、ほぼ唐文明の水準に達したことを示している。それ以来、世界の文明水準から日本史が大きく劣後したことはなかったと思われる。文化の日本国内における爛熟期である平安時代には、世界の文学である『源氏物語』が生まれた。やがて応仁の乱になり、戦国時代という血で血を洗う内乱の悲惨な時代を迎えたが、そういう中でも種子島と呼ばれた銃が伝わると、およそ50年のうちに世界最大の銃の保有国、生産国になった。長期にわたる戦乱と統治不能の時代にも復元力が働き、信長、秀吉、家康による再統一が成し遂げられた。平和な徳川時代でも、社会統治や技術、社会政策、江戸文化、識字率は同時代の西洋に劣らない水準を保っていた。
ただ鎖国をしている間に、イギリスを中心に産業革命が起こり、日本は近代西洋文明に遅れた。やがて黒船来航を契機として、尊皇攘夷の志士が西洋人に襲いかかるという野蛮な仕方で自立心を表現しながらも、他方で西洋文明を猛然と学んだ。そしておよそ50年の学習を経て日露戦争に勝利した。このことは、近代日本が西洋文明に近い水準を築いた最初の非西洋社会であることを示すものであった。対外的な危機だけでなく大災害という国難に対しても、日本は常にばねを利かせて大いなる復興を果たしてきた。
この列島の住人は歴史的に豊かな自然に抱かれて農業、漁業を生業としてきた。この豊かで優しい自然は、しかし時として荒れ狂い、牙をむいて暴虐の限りを尽くす。そのときは首をすくめて何とか生き延び、そして台風一過、津波一過、また翌朝より槌音高く一致協力し、勤勉に働き、また同じ場所に木と草と土でできた同じ家を建てるということを繰り返してきた。
しかし、全くそうであるとは言えない。1896年の明治三陸大津波の際に、ある町長は「被災した低い土地に家を建ててはならない、高台に建てよ」と指導し、その子孫はこのたびの津波から助かった。一方で、住民たちは不便という代償を払わされた。不便を代償にせねばならなかった明治時代と違い、今では丘の上のニュータウンは、全国至る所で見受けられる情景である。
われわれは新しい歴史を作る瞬間を迎えているのではないか。津波に対しては「逃げる」ほか助かる術はない。個々に逃げるだけでなく町ごと逃げる。海を見下ろす丘の上に新しいコンパクトな町を作り、そこには単に住居だけでなく、小学校、老人ホーム、病院、包括ケアのセンターを設ける。ただ、そのためのお金がかかる。莫大なお金をかけてまでやらなければいけないかどうかデリケートな問題であるが、東日本大震災復興構想会議の私どもの報告書では、地理的条件が許すなら、もっとも望ましい第一類型として高台への移転を提示した。ただ広く多様な被災地を一つにくくることはできない。五つの類型を示し高台移転に対抗するプランとして同じ地にさまざまな減災手段(防波堤、防潮堤、二線堤などと、個人住宅の二線堤より内陸部への移動)を組み合わせての「多重防御」を第三類型として示した。
次のような指摘がなされた。「阪神・淡路大震災のときには、大企業で働いているサラリーマンが多く、大企業は社員の安全を図るとともに給料を支給しており、ほぼ家のみが問題であった。しかし、今度の東日本大震災では、第一次産業関係、自営業、農業、漁業に従事する人が多く、家よりも生業が問題である。家も大事だが、それ以上に仕事の再建が大事だ。」
自然災害の歴史を振り返ると、一つの災害を思って対処すると、それを外して別のものがやって来るという傾向がある。国際関係の分野には、「将軍たちは前の戦争を戦い、外交官たちは前の講和会議を交渉する」という言葉がある。一つ覚えで考えては当てが外れる。記念講演で貝原理事長は関東大震災、阪神・淡路大震災、東日本大震災の「三つの大震災」について論じた。三つの大震災を比較して検討し、視界に入れると、そのバリエーションの中で多くのものを見ることができる。
関東大震災は相模湾を震源とするマグニチュード7.9の地震に始まり、直下型を含めて三つの連鎖地震が関東を襲い、そして火災も発生した複合災害であった。地震そのものによる倒壊・圧死が1万人、焼死が9万人であり、強風という自然条件の重大さをきわ立たせた。それに対し復興については、後藤新平の力強いリーダーシップの下、大日本帝国の首都建設という創造的復興の大方針が打ち出された。近代西洋を猛然と学習する中で、西洋一流国に劣らない首都を日本が持つ契機として生かそうとした。後藤プランは政治的に破れて挫折したが、首都東京のマスタープラン、集合住宅、都市計画、小学校の横の公園などは、後藤プランが大幅に縮小された後も生き延びて、立派な東京の土台になり、日本各地の都市のモデルにもなった。
阪神・淡路大震災では6434名が亡くなったが、約9割が家屋倒壊による圧死であった。非常に純度の高い単純直下型の地震災害であり複合災害にはならなかった。もし強風が吹いていたら、火災も劣らぬ犠牲を出す複合災害であり得たかもしれない。昼間であれば、新幹線やJR、私鉄の列車が高架から転落するというような複合災害化したかもしれない。あるいは、もう一つの活断層である有馬高槻構造線の地震が連動した場合には大変なことになったであろうが、幸いにも単純な直下型地震災害で終わった。
阪神・淡路大震災当時の兵庫県知事であった貝原理事長自身が語るように、兵庫としては高度成長以後の時代を見据え、高齢化が進む経済先進国日本を先導するモデルにふさわしい創造的復興を願った。しかし政府にはそのような発想はなく、復旧のためには国費を投ずるが、それ以上の復興には国費は用いてはならないとした。そのことが日本全体の創造性や活力を殺ぎ、「失われた20年」への沈論を招いたのではないか。国がよりよい復興を支持しないなか、兵庫は地域自前の努力で、淡路夢舞台や神戸東部新都心、医療産業ゾーン、文化面では県立新美術館や西宮の芸術文化センターなどを設立し、それが大きな遺産になっている。
東日本大震災では、宮城県栗原市は震度7であったが、犠牲者は出なかった。日本社会が震災に対して極めて強靱な社会になっていることが示された。被災者の振る舞いが立派であるというだけでなく、震度7にも犠牲者は出なかった。また、東北3県を走っていた上下10本の新幹線は緊急地震速報のシステムが作動して全部事故を起こさずに止まった。国民、社会の現場力というものが相当に高いものであることを示したが、津波によって2万人余りの犠牲を出し、さらに原発事故を併発して大複合災害となった。
阪神・淡路の際は、初動が遅かった自衛隊が、この度は交通・通信システムが寸断した中、初期の人命救助や道路啓開、生活物資運搬などで圧倒的な役割を果たした。
阪神・淡路大震災はボランティア元年と呼ばれ、130万人ものボランティアが神戸の救援に駆けつけた。今回の東日本大震災については、地理的遠隔に加えて、原発事故による放射能への恐怖もあり、数的にはその半分レベルにも至っていない。しかし遠野市を拠点とするNPO支援体制や、企業・大学などによる組織的なボランティアの派遣、さらには、兵庫県を先頭とする自治体間の広域的な連携・支援など、阪神・淡路大震災のときにはなかった、進んだ対応も認められる。
また、神戸のときには躊躇した外国からの救援を、このたびは日本政府が潔く受け入れ、28の国から救援隊が駆けつけてくれた。2万のアメリカ軍が来援し、「トモダチ作戦」により、大きな力を発揮した。オーストラリア軍も輸送力を発揮した。われわれは外国をODAで支援してきたが、助けてもらうマナーというのは意外に難しい。かえって迷惑だという反射的な対応がいつも起こるが、今回、それを超えたのは一つの前進である。
阪神・淡路大震災のときのように、政府が復旧にはお金は出すが、復興については自分でやれということは、東北地方に対しては悲惨な結果になるであろう。東北被災地に対し、国、国民全体で出来るだけのことをすべきだと、復興構想会議は考えた。「連帯と分ち合い」によって、全国民が被災地を見捨てず、支え抜くことを根本精神としています。とはいっても、財源を考える、増税をするということになると、一般に政治はたちまち腰が重くなる。それを超えて今回のプランは、日本国民全体が助け合って生きていく原点を説いた。その息吹、馬力が日本全体の再生にとってもプラスになることを期待したい。
「失われた10年」「失われた20年」といって、徐々に衰退していくプロセスにあった日本は、このたびの大災害を受けて、ゆっくりと衰退するシナリオを切断して飛び上がる機会を得たと考えたい。国民全体で被災者を見捨てずに何とかしようという努力の中で、自らもまた救われるシナリオを求めたい。
今回の淡路会議の重要な課題は、高齢化時代における福祉、それも活力ある福祉社会のあり方を考察することである。日本全体が猛然と高齢化社会に疾走している。そしてアジアの韓国や中国などがまた猛然と高齢化社会に疾走している。そういう中で、日本が高齢化社会にとって妥当な福祉社会モデルを築くことができれば非常に大きな意味を持ちうるであろう。
基調提案が指摘するように、日本人は60年代までは、自宅で死を迎えるのを常としていたが、70年代からは病院にお世話になり病院信仰が極めて高くなった。臓器治療技術の革新により病院へ行けば助かる、今や長寿を全うして病院で死を迎えるのが日本人の様式になってきた。そのことが果たして幸せなことなのかどうか。大事なことは病院で臓器を治療してもらうこと以上に、病の予防、健康維持に比重を置いて、よく食べ、よく動き、生活の場でケアや在宅医療を受けて元気に過ごす。できればピンピンコロリでなく、ピンピンキラリであるとの発言もあった。そういう地域のケアがヒューマンネットワークの形成と表裏一体でなければならない。
そうした新しい社会のために、福祉産業がハードの面でもソフトの面でも発展せねばならない。ハードでもソフトの面でもイノベーションが必要である。福祉産業の需要が経済を活性化していく活力ある福祉社会の可能性が議論された。高福祉・高負担の社会は活力を失って、成長力を失うという通念があったが、スウェーデンのような北欧の例はそれを支持しない。高福祉社会への進展が高いGDP、高い成長力を支える要因ともなし得ることが議論された。
高齢化と表裏を成す少子の問題は、日本の場合、非常に深刻であるが、女性の就業と子育ての両立を可能にする社会を求めていかねばならない。二人以上の子を育てることに対し、現状の日本社会は禁止的であるとすらいえるが、この両立をサポートする社会環境を整備し、充実させる覚悟をどこかで決めていかなければならないのではないか。同時にスウェーデンの例でも、ボルボやノキアに示される国際競争力のある輸出産業の健在も無視することのできない要因がある。これらとともに、福祉の内需が活力ある社会を支える要因になり得ます。
急速な高齢化を迎える日本社会に、時間的余裕は少ない。しかもこの大国難の中で、果たしてわが社会や、政治に何ができるのか、政治が国民に負担を説得できるのか。国家社会の制度的対応とともに、この会議で強調されたのは、そういう政治社会の内側の心の問題であった。心の働き、文化の側面の重要性が語られた今回の会議であった。
このたびの東日本大震災でも、たくさんの義援金が届いたが、それに劣らず、ミュージシャンやアスリートがチャリティのイベントを次々に行う、そのこと自体が大変なメッセージとなった。それに被災地の人は励まされる。なでしこジャパンが優勝すれば、被災地の人も涙する。そのような共感、感動を持てば、体内の何かをオフからオンに替え、若返らせることができる。ボランティア活動に出掛けた若者が、今まで受太刀で消極的だった若者が、人が変わったように、これからはわれわれ若者がやっていくのだと振る舞うようになったとの報告もあった。閉じこもらないで、人々とつながり、やる気、気概を示す人。幸福、救いというものは心にある。そういう心がみなぎる活力ある社会でなければならない。
日本には文化の豊かな伝統があります。芸術、スポーツ、科学技術の諸分野にまたがるクリエイティビティ・インデックスではスウェーデン、日本が1、2位であるという。そのような良き伝統の上に立って、日本が新しい活力のオフをオンにしていく。それは、詰まるところ人間の問題であるというのが、このたびの2日間の会議で教えられたところである。科学技術文明に酔いしれてきた近代人、日本もその模範生であったが、例えば西洋医学の臓器治療に邁進し、大きく寿命を延ばす点で支えてきたが、そこまで来て、患者中心、人間中心、魂を含めた人間の全体性への感覚を持った社会を甦らせたい。物的、制度的基盤に劣らず、人間の全体性への感覚を豊かに持った共生社会ということの重要性を、このたびあらためて認識した。それをどのように全社会化していくかについて、いろいろなアイデアを結び付ける、つなぐ役割を活性化しなければいけないという指摘がなされ、参画する社会をもたらす国家制度についても、貴重な提案がなされた。結論を一言でまとめるには、余りにも人間と社会についての深い問題が論じられ、数多くの深い洞察が語られたこのたびの会議であった。