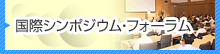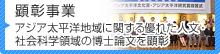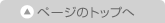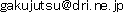第25回「アジア太平洋フォーラム・淡路会議」国際フォーラムの概要
第25回「アジア太平洋フォーラム・淡路会議」国際フォーラムの概要

- プログラム
-
- 日時
2024年8月2日(金)
10:30~17:00 - 場所
兵庫県立淡路夢舞台国際会議場
(兵庫県淡路市夢舞台1番地) - テーマ
「どうする日本、どうなるアジア ~AI・メタバース・水素と共生する社会」 - 内容
- ○開会挨拶
- 牧村 実
- (アジア太平洋フォーラム・淡路会議代表理事)
- ○第23回アジア太平洋研究賞受賞者紹介
- ○記念講演
- ◆記念講演
- 「日本におけるDX推進の課題と展望」
- 講師:河野 太郎
- (自由民主党衆議院議員、デジタル大臣、デジタル行財政改革大臣、デジタル田園都市国家構想大臣、行政改革大臣、国家公務員制度担当、内閣府特命担当大臣(規制改革)) オンラインによる講演
- ○開会挨拶
- 日時
- ①「脱炭素社会実現に向けた水素技術の社会実装について」
- 講師:原田 英一
- (川崎重工業株式会社シニア・エグゼクティブフェロー)
- ②「メタバースと最先端技術が導く未来の産業」
- 講師:本城 嘉太郎
- (mono AI Technology 株式会社代表取締役社長)
- ③「AIと統治:グローバル・ガバナンスとデジタル立憲主義」
- 講師:工藤 郁子
- (大阪大学社会技術共創研究センター特任准教授)
- 第1分科会
- 「新技術の活用による日本企業の生き残り戦略」
- 座長:中尾 優
- (弁理士法人有古特許事務所長・弁理士)
- 第2分科会
- 「AI等活用による産業・雇用の創出」
- 座長:永吉 一郎
- (株式会社神戸デジタル・ラボ会長)
- 第3分科会
- 「AI時代の意思決定のあり方」
- 座長:梶谷 懐
- (神戸大学大学院経済学研究科教授)
- 阿部 茂行
- (ひょうご震災記念21世紀研究機構参与)
- ◇記念講演 「日本におけるDX推進の課題と展望」
- 河野 太郎(自由民主党衆議院議員、デジタル大臣、デジタル行財政改革大臣、デジタル田園都市国家構想大臣、行政改革大臣、国家公務員制度担当、内閣府特命担当大臣(規制改革)) 1.わが国の課題とデジタル化
■記念講演の概要■
日本は、年80 万人というかなり速いペースで人口が減少しており、平均年齢は49 歳となった。一方、インドやサウジアラビアの平均年齢は20 歳代なので、日本の平均年齢は世界的に見てかなり高い状況だ。
日本のあらゆる地域で人口減少・高齢化・過疎化が進む中、人が人に寄り添う温もりのある社会をつくるためには、人間は人間がやらなければならないものに集中し、人間がやらなくてもいいものは、めりはりをつけてAI(人工知能)やロボット、コンピューターに任せていかなければならない。
2.デジタル化の進む諸外国
諸外国では、コロナ禍でデジタル化がかなり進んだ。例えばインドは、コロナ渦以前、かなりアナログな社会だった。農家が生産物の対価を受け取るとき、町で100 ルピーを渡すと、渡された人がその中から1 ~ 2 割抜いて次の人に渡し、次の人もまた中抜きして、最終的に農家には10 ルピーしか渡らないという状況が続いていた。今では携帯電話で瞬時に相手に送金できるようになり、いろいろなものが一気にデジタル化された。
またUAE(アラブ首長国連邦)では、赤ちゃんが生まれると病院から政府に情報が発信され、出生証明書、国民としてのIDカード、パスポートの3 点セットが3 日以内に届くそうだ。リープフロッグといわれるように、諸外国では社会を一気に変えようとしている。
3.日本でデジタル化が進まない理由
日本の場合、マイナンバーカードと保険証のひもづけ誤りが8,000 件判明し、随分お叱りを頂いた。諸外国でこの話をして、母数は1 億2,000 万件だと付け加えると、「0.007%か。さすが日本はすごいな」と褒められる。日本には完璧を求めるゼロリスク信仰があり、新しいことをやりづらいが、一つずつ乗り越えて、温もりのある温かい社会をつくるためのデジタル化を進めていきたい。
4.規制がデジタル化のネックに
物流の2024 年問題といわれるように、トラックによる配達の継続が難しい状況となっている。中心部から離れた小さな集落までトラックで配達すると配送効率が極端に落ちるが、ドローンで配達できれば配送効率を高められる。しかし、規制によってドローンが道路を横切るときは、「ドローンに注意」という看板を立てなければならなかった。
また、ドローンから荷物を下ろすのが一番リスクが高いので、荷物を下ろす場所に人を派遣して管理する必要があった。でも人が現地に行くのであれば、その人が荷物を配達すればいいわけで、ドローンを飛ばす必要はなくなる。ドローンにカメラを付け、カメラで周辺の安全を確認できれば降りて、荷物を置いてまた飛び立てばいいのではないか。ドローンについては、担当大臣として昨年12 月に規制改革を行い、「レベル3.5」という区分を新設し、今のような規制をなくした。
このように、技術があっても規制を撤廃しないと活用できないので、デジタル庁に専門のチームを立ち上げ、明治元年制定の法令までさかのぼってチェックし、アナログを義務付けている条文を全て削除した。
5.マイナンバーカードの活用
マイナンバーカードにはICチップが入っていて、さまざまな本人確認に使うことができる。神奈川県平塚市や兵庫県姫路市、宮崎県都城市では、全国に先駆けて救急車内でマイナンバーカードを読み取ることを始めた。救急車を呼んだとき、気が動転していたり、具合が悪いため状況を正確に伺うのが難しいし、「薬は白くて丸いやつを1 日2 錠」と言われてもよく分からないことがある。
救急車内でマイナンバーカードを読み取ることで、今から病院に搬送する○○さんはどんな薬を飲んでいて、糖尿病と高血圧の症状があることを伝えることができる。
マイナンバーカードを常に携帯していただくことで、行政サービスの質を上げることができる。
6.自治体システムの共通化
これまで1741 の市区町村がそれぞれシステムを構築し、運用していた。地方税や社会保険、児童手当などのルールが変わるたびに各自治体が一斉にシステムを修正し、それぞれ莫大な金額をベンダーに払ってセキュリティを確保しなければならない。今後の日本を考えると、これは持続可能ではないと思う。
今後は国がシステムを一元的に構築し、メンテナンスやサイバーセキュリティの確保も国が責任を持って行うので、自治体は国が提供するシステムを使うようにすべきだ。政策は自治体の判断によるが、システムは共通で、書類の様式も統一するのが合理的だと思う。
7.デジタルディバイドの解消
デジタル化が進む自治体にはリーダーシップがある。リーダーが方向性を示し、部下に対しても「やってみろ。うまくいかなかったら俺が責任を持つ」と言って鼓舞することが大切だ。
コロナ禍でワクチン接種を進めたとき、当初、厚生労働省は自治体に通知をたくさん出して様々な手続きを求めたため、なかなかワクチン接種が進まなかった。ワクチン接種担当大臣だった私は、ワクチンの温度管理とロット番号の管理、接種記録を付けることだけを守ってもらい、あとは自治体に任せたら、いろいろなやり方でスピードアップしてくれた。日本の自治体の現場力は非常に優れている。その現場力を引き出すにはリーダーシップが大事だ。
8.「行かない役所」「書かないワンストップ窓口」
デジタル庁では「行かない役所」つまり行政手続きを全てスマートフォンでできることを目指しており、役所や役場では「書かないワンストップ窓口」を導入している。マイナンバーカードで本人確認できれば、何の手続きをしたいか口頭で言うだけで、いろいろな窓口を回らなくても手続きを完結することができる。
行政サービスを誰にとっても今よりはるかに便利にしたいと思っている。デジタルに詳しい人はデジタルで、デジタルが苦手な人は裏側のデジタル技術でもっと便利にし、皆さんの暮らしを今まで以上に便利で豊かにすることができると思っている。
■基調提案の概要■
- 「脱炭素社会実現に向けた水素技術の社会実装について」
- 原田 英一(川崎重工業株式会社シニア・エグゼクティブフェロー水素事業推進担当)
当社では一昨年、「グループビジョン2030」を定め、「カーボンニュートラルの実現と経済安全保障」「安全安心な高齢化社会の実現」「安全安心な国際関係」の三つを注力分野として掲げている。その中の「カーボンニュートラル実現と経済安全保障」の一つの大きな流れとして、水素による脱炭素社会の実現を推進している。日豪パイロットプロジェクトでは、CO2の排出を抑えながらエネルギーの安定供給を実現できる液化水素の国際サプライチェーンの構築を目指している。
液化水素運搬船「すいそ ふろんてぃあ」は、マイナス253℃の液化水素を高度な断熱技術を用いた真空二重構造のタンクによって安全、安定的にかつ効率良く運べることを実証した。現在商用化をめざしている船のタンクの容量は4 万~ 16 万m3 で、タンクを大規模化して一度に大量に運ぶことで流通コストの低減を目指している。受入基地のタンクも、現在は1 基当たりの容量が2500m3だが、5 万~ 20 万m3を目指して技術開発を進めている。脱炭素を目指すにあたり、水素はあらゆる選択肢を補完・サポートできる。脱炭素を担うため、われわれは水素技術の社会実装を進めたい。
- 「メタバースと最先端技術が導く未来の産業」
- 本城 嘉太郎(mono AI Technology 株式会社代表取締役社長)
当社は元々ゲーム会社だったが、XR(クロスリアリティ)やメタバースの領域で一昨年上場した。上場前にソニーグループなどから約15 億円を調達し、「XR CLOUD」というメタバースプラットフォームを作った。メタバースとはインターネットと同じぐらい何でもできるが、バーチャルライブ、展示会、学校など様々な要望にあわせて毎回ゼロから作りあげるのは大変だ。XR CLOUDという共通基盤上に、学校用であればセキュリティの高いID機能や先生が生徒の画面を見る機能、バーチャルライブ用にはチケット販売機能や投げ銭機能など、各目的に特化した機能を加えたメタバースを提供している。
OpenAI 社のサム・アルトマンは「今後、生成AIによって仕事がなくなるというより、タスクがなくなるだろう。生産性は2 ~ 3 倍ではなく20 ~ 30 倍に上がるだろう」と言っている。デジタル化できた業務はAIにとって代わられるということは、逆に言うと自分たちの仕事をデジタル化すればAIによる自動化の恩恵を最大限受けられる時代が来るということではないか。
- 「AIと統治:グローバル・ガバナンスとデジタル立憲主義」
- 工藤 郁子(大阪大学社会技術共創研究センター特任准教授)
デジタル立憲主義は、AIを開発・提供する巨大テクノロジー企業も国家に匹敵する力を持った存在だと認識し、デジタル空間も対象とする統制が必要だという考え方だ。
OpenAI 社自身も、生成AIが社会的バイアスや特定の世界観を強化し、阻害されたグループに対する偏見や侮辱的なコンテンツを再生産することを懸念している。これはAIの学習に使われるデータセットが北米に偏っていて、アジアやアフリカ、中南米の視点を反映していないと問題視されている。
AIのバイアスが大きいと、私たちがこれから見つける科学技術や研究開発の知見もゆがめられる可能性がある。バイアスが少なく、現実世界をより適切に反映できるかどうかは、私たちの今後の認識や研究開発能力をも左右し、ひいては、私たちの健康や考え方にも影響を与える可能性がある。
今後のAIとの付き合い方や向き合い方、AIをどう統御、統治していくのかを考えることが必要だ。
■分科会の概要■
- 第1分科会 「新技術の活用による日本企業の生き残り戦略」
- 報告者 中尾 優(弁理士法人有古特許事務所長、弁理士)
第1 分科会では、講師の原田氏をお招きして、「新技術の活用による日本企業の生き残り戦略」というテーマで、水素ビジネスに関連する議論を深めた。水素ビジネスの特徴としては、オーストラリアと共同プロジェクトを行うとともに、国際的な基準認証を同時並行的に取得しながら事業を展開している点が挙げられる。
そういう意味からも、外国公館の方に興味と関心を持っていただけたテーマだったのではないかと感じた。具体的には、ドイツ公館の方から、ドイツではグリーン水素や再生可能エネルギーの導入が進んでおり、日本以上にチャレンジングな取り組みがなされているという話があった。ロシア公館の方から、水素の供給源を現実的にはどう考えているのか、燃料電池自動車や電気自動車といった脱炭素のモビリティの取り組みがある中、どのようにそういう状況を考えるのかといった質問があった。ベトナム公館の方から、水素を含む脱炭素化の取り組みをする上でコストはどう考えているのかという質問があった。それらに対して、適宜いろいろな意見や感想を述べて議論を進めた。
今回、「新技術の活用」と「日本企業の生き残り戦略」というテーマに沿って、私見を申し上げると、日本企業の外国ビジネスとしては他にあまり例がないのではないかと感じた。2030 年の水素技術の商用化に向けて、今後もそのような取り組みがいろいろ展開されるかもしれない。
本日参加された外国公館の方とも話をしたが、オーストラリアと東南アジア諸国とを結ぶ水素の懸け橋としてのビジネスが日本企業としての生き残り策であり、「日本から」「日本で」「日本政府が」という文脈ではなく、本籍地は日本の企業であるけれど、その技術を第三国で展開するチャレンジングな取り組みに積極的に参加していきたいし、そのためには技術開発もさることながら、他国での理解を得られるように取り組み方、受け入れられるように取り組む姿勢、仲間づくりのようなものも非常に重要になると感じた。
2030 年の商用化には紆余曲折があろうかと思うが、このような取り組みに接する機会があったことは、後で思い返すと非常に意義のあるものになり、新しい日本企業の歴史の1 ページになったと思える日になればいいと思っている。
- 第2分科会 「AI等活用による産業・雇用の創出望」
- 報告者 永吉 一郎(株式会社神戸デジタル・ラボ会長)
第2 分科会では「AI等活用による産業・雇用の創出」ということに関して議論した。
まず、産業・雇用の創出という以前に、皆さんは、AIが普及することで人間の仕事が奪われるのではないかという懸念を持たれると思うが、講師の本城氏から、実はもっと大きなリスクがAIにあるということが示された。
皆さんの会社や組織でもAmazon のAWS(Amazon Web Services)を使っておられると思うが、会社の中心的なシステムを動かしているクラウドサービスがある日突然、大規模に停止する可能性がある。
これと同じことがOpenAI でも起こる可能性がある。アメリカのジャイアントITが皆さんに提供しているAIのエンジン部分はアメリカで運用されていて、これが止まると全部停止するというリスクがある。このため、日本政府も国内製AIを作ろうと努力している。
一方、ある研究によると、ChatGPT の出来は70 点程度で、100 点になるかどうかはまだ分からないし、せいぜい効率化される仕事は5%ぐらいだろうと言われている。AIの普及によって生まれる新たな仕事も当然ある。
例えば障害者や高齢者が自由に働ける未来だ。これはAIだけではなくメタバースも含まれてくるが、メタバースには無限の可能性がある。一例を挙げると、東京のオリィ研究所が展開しているロボットバーだ。バーに小さなロボットが置いてあり、一つ一つに名前が付いていて、遠隔地にいる障害を持った方や職場に働きに行くことができない方が、お客さんが来たらオンラインでアクセスし、会話と動きで客の相手をするというものだ。いつも満員だそうだ。このように誰もが、どこにいても何でもできることがメタバースやAIの人間を幸せにする機能の一つだと考えている。それから、日本の大きな課題の解決ということでは、例えば言葉の問題がある。日本人の英語が苦手なことは世界でも有名だが、AIによって自動翻訳のレスポンスはどんどん向上しており、実測0.2 秒で、ほぼ会話についていけるスピードになっている。ストレスなく海外の方とコミュニケーションが取れる時代がもうすぐやって来る。
- 第3分科会 「AI時代の意思決定のあり方」
- 報告者 梶谷 懐(神戸大学大学院経済学研究科教授)
第3 分科会では、工藤郁子先生の基調提案を踏まえ、「AI時代の意思決定のあり方」について非常に活発な議論が展開された。
1 点目は、AIのような技術を発展させる際に、産業政策の観点から政府がどのように介入するかという論点だ。EUのデジタル立憲主義は、EUと米国の産業構造の違い、特にデジタル・ITの産業に関する進歩の差をいかにキャッチアップするかということだ。技術的に米国企業が先行するのは、果たして人権や立憲主義のような価値観に照らして問題はないのかという観点から、キャッチアップを図っていくしたたかな戦略がある。中国でGAFAに対抗してバイドゥのような企業が台頭してきた背景には、いわゆるデジタル輸入代替主義、GAFAのサービスを制限することで自国の産業を育てていく戦略があった。こうした産業政策で先端技術を発展させようという動きが世界各地にある中で、日本はどのように考えていけばいいのかという点が重要だ。
2 点目が教育の重要性である。AIのような最先端技術を理解し使いこなす、あるいはそれを統治するときにデータサイエンスやIT技術に関するリテラシーが必要になる。既存の教育体系の硬直性をいかに破っていくかが重要だ。例えば文系・理系といった枠組みの中では、いかにデジタル技術を統治していくかという知の在り方はなかなか生まれない。そうしたものを打破するため、個人レベルで大学の既存学部の枠組を越えるか、あるいは政府が高等教育をデザインしていくかが重要になってくる。
3 点目はいわゆる普遍的な価値観の問題だ。どんどん発展する先端技術、AIもそうだが、人権にもとるような技術は制限しなければならない。また、市民が打ち立てたルールに基づきそれを運営しなければならない。立憲主義は重要だが、反面そこを強調し過ぎると、普遍的な価値観といいつつ西洋中心的なバイアスに陥いる危険性がある。工藤先生の話にもあったが、生成AIなどが利用するデータは地域的に偏りがある。このため人種によって非常に不利な扱いを受けるような判断をAIが下してしまう恐れがある。データの偏りはもちろん、それを制御すると期待される立憲主義や人権といったものが、往々にして非西洋的な地域の人々からすると、自分たちの考え方や体制といったものを排除する道具として使われる懸念がある。デジタル技術を制御する際には普遍的な価値観が重要だが、それが西洋中心的なものに陥らないようにするうえで、日本の知見が非常に大きな役割を果たすのではないか。