| A 安全安心 | 安全安心・国際貢献 | |
| 開催日・テーマ・講師 | 講義内容 | 配付資料 | |||
| 平成25年10月2日(水)
13:30~15:00 |
東日本大震災では、阪神淡路大震災時を上回る海外からの支援が寄せられた。人的支援、物的支援とも、支援の窓口は外務省であり、同時に内閣府におかれた緊急災害対策本部の「事態対処班(C7班)」が支援を受入れるかどうかについての連絡調整を行った。 阪神淡路大震災時の反省に基づき詳細なマニュアルが作成されていたため、多くの作業が円滑になされたが、震災の規模の大きさと東京電力福島第二原子力発電所の事故が重なり、少なからざる点で、今回も混乱がみられた。この経験から、来るべき災害に際して、私たちは何を学習すべきかを、外務省や消防庁等の、当時、海外からの支援受入れを担当した人たちからの聴き取り調査に基づき明らかにしたい。 | 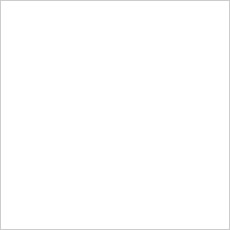 |
|||
| 東日本大震災と海外からの支援受入れ;外務省を中心に | |||||
| 東日本大震災、海外からの援助受け入れ、外務省 | |||||
| 片山 裕 | |||||
| (公財)ひょうご震災記念21世紀研究機構研究調査本部政策コーディネーター 神戸大学大学院国際協力研究科教授 |
|||||
| 配付資料 | |||||
| 平成25年10月23日(水) 13:30~15:00 |
阪神・淡路大震災をきっかけに、日本の地方自治体の災害対応のあり方、とりわけ発災時の初動対応のあり方には大きな変化が生じた。具体的には、国ないしは中央政府主導のもとで行われる支援だけではなく、応援協定等にもとづく地方自治体の自発的な支援も活発に行われるようになった。言い換えれば今日においては、いかなる自治体間ネットワークを構築しているのかが、大規模災害時における被害の低減を検討する際には重要となってきているのである。そこで本報告では、この自治体間ネットワークという観点から今日における地方自治体の災害対応のあり方について、関西広域連合によるカウンターパート方式などやや特殊な支援方式も参考にしつつ検討する。 | 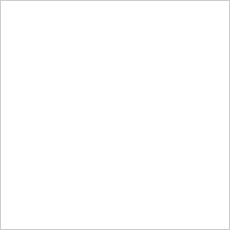 |
|||
| 地方自治体の災害対応と自治体間ネットワーク | |||||
| 広域防災、広域連合、ネットワーク | |||||
| 善教 将大 | |||||
| 東北大学国際高等研究教育機構助教 | |||||
| 配付資料 | |||||
| 平成25年11月1日(金) 13:30~15:00 |
本講義では、①関東大震災、②阪神・淡路大震災、③東日本大震災、の三つの大震災の復旧・復興過程について、政治史・行政史の観点から比較検討を行う。 過去の大震災に際して、中央政府や地方自治体といった行政機関はいかなる対応をとったのか、また首相や首長らの政治リーダーたちはいかなる手腕を発揮して災害からの復興を実現したのか。この問題について、当時の一次資料やオーラル・ヒストリーなど最新の成果を踏まえて解説する。 | 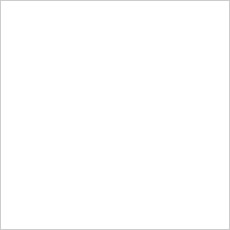 |
|||
| 大震災復旧・復興過程の比較 -関東、阪神・淡路、東日本大震災を中心に- | |||||
| 復旧・復興、行政、比較研究 | |||||
| 渡邉 公太 | |||||
| (公財)ひょうご震災記念21世紀研究機構研究調査本部研究員 | |||||
| 配付資料 | |||||
| 平成25年11月20日(水)
13:30~15:00 |
本講義では、大規模な災害が発生した際に、被災地に対して行う復旧・復興の支援をどのような行政の枠組みで行うべきかについて考えます。この際、参考となるのが、東日本大震災の際に、関西の2府5県が結集し設立された自治体間の連携組織である「関西広域連合」の行った支援です。関西広域連合は、支援する自治体と支援を受ける自治体との間でペアを作る「カウンターパート方式」を採用し、迅速な対応を行ったとされています。講義では、こうした東日本大震災時の関西広域連合の支援活動の評価と課題について、関西広域連合の設立経緯にも言及しつつ、国や他の個別自治体による支援との比較を行いながら検討します。 |
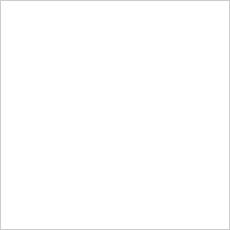 |
|||
| 自治体間連携による災害支援と防災政策 ―関西広域連合の活動を中心に | |||||
| 自治体間連携、関西広域連合、復旧・復興支援、防災政策 | |||||
| 梶原 晶 | |||||
| (公財)ひょうご震災記念21世紀研究機構研究調査本部研究員 | |||||
| 配付資料 | |||||
| 平成26年1月24日(金) 13:30~15:00 |
大地震などの自然災害の緊急・復興支援には、政府や地方自治体、国内の関係機関に加えて、国連等や国際NGO等が大きな役割を果たしている。日本国内では、東日本大震災において初めてこうした国際NGO等が緊急復興支援活動を大規模に展開した。本講義では、過去の事例や東日本大震災でのこれら国際NGO等の支援を教育分野での支援に焦点を当てながら紹介する。 | 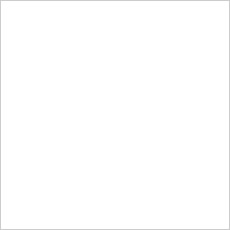 |
|||
| 震災復興における国際NGOの役割(仮題) | |||||
| 震災復興、NGO、人道支援 | |||||
| 桜井 愛子 | |||||
| 神戸大学大学院国際協力研究科特命准教授 | |||||
| 配付資料 | |||||
| 平成26年2月28日(金)
13:30~15:00 |
東日本大震災時、日本には、多くの国・地域・国際機関から、レスキューチームの派遣や物資・寄付金の提供等、温かい支援が寄せられました。これら支援の受入れについて、当時の日本政府はどのように対応したのか、どのように阪神・淡路大震災時の経験が活かされていたのかについて、ご説明させていただきます。 また、海外で大規模な災害が発生した際に日本が派遣する国際緊急援助隊(JDR)の活動についてもご紹介します。 | 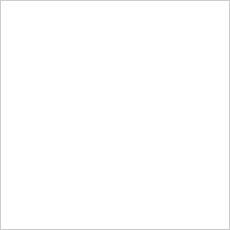 |
|||
| 東日本大震災における海外からの支援受入れについて | |||||
| 東日本大震災、海外支援、救援チーム、救援物資 | |||||
| 大江 伸一郎 | |||||
| 内閣府 政策統括官(防災担当)付参事官(普及啓発・連携担当)付国際防災協力専門官 | |||||
| 配付資料 | |||||