| 開催日・テーマ・講師 | 講義内容 | 配付資料 | |||
| 平成25年10月11日(金) 13:30〜15:00 |
水害や津波などの災害の発生危険時や、その後の復旧・復興過程では、さまざまな防災情報が行政機関から発表になり市民に伝えられます。その際には、スマートフォンなどの新しいメディアとともに、ラジオなど古くからのメディアも活躍しています。さらに最近では、市役所などから市民にむけて一方向的に情報が発信になるばかりではなく、市民自らが、情報を集めたり発信をするすることも多くなっています。本講義では、こうした市民の活動にも着目して紹介します。 | 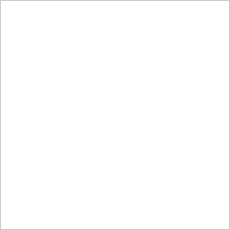 |
|||
| 市民による防災情報の発信・受信 | |||||
| 情報、市民メディア、ラジオ、ケーブルテレビ | |||||
| 宇田川 真之 | |||||
| (公財)ひょうご震災記念21世紀研究機構人と防災未来センター研究主幹 | |||||
| 配付資料 | |||||
| 平成25年10月25日(金)
13:30〜15:00 |
南海トラフで発生が懸念されているマグニチュードの大きな巨大地震では、長周期の揺れが震源からたっぷり放出される。さらに、南海トラフ周辺には付加体と呼ばれる長周期地震動を伝えやすい堆積層が堆積している。その上、東京・大阪・名古屋などの大都市は、大規模堆積平野に位置しており、長周期の揺れが増大・伸長しやすい。ここに、長周期で揺れやすい高層建物や免震建物が林立している。来るべき巨大地震を前に、長周期地震動対策をどのように進めれば良いのか考える。 | 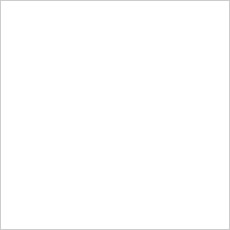 |
|||
| 長周期地震動による被害と対策 | |||||
| 長周期地震動、高層建物、免震建物、南海トラフ巨大地震 | |||||
| 福和 伸夫 | |||||
| (公財)ひょうご震災記念21世紀研究機構人と防災未来センター上級研究員 名古屋大学減災連携研究センター長・教授 |
|||||
| 配付資料 | |||||
| 平成25年11月13日(水) 13:30〜15:00 |
現在も宮城県支援に赴いているが、被害の程度や種類、あるいは都心部と郡部という違いはあるものの、阪神・淡路大震災後と同じような問題が起きている。当時、中長期のこころのケアを行うため設置した「旧兵庫県こころのケアセンター」の運営に携わった立場から、東日本大震災にも通じるであろう“こころのケアの課題”“こころのケア に必要なこと“などに言及したい。 | 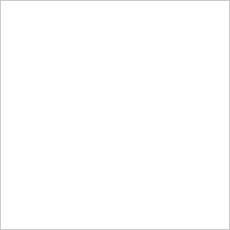 |
|||
| 災害とこころのケア −阪神・淡路大震災と東日本大震災の支援から− |
|||||
| 災害の反応、二次的ストレス、健康・生活支援、 地域での多層的サービス、支援者のメンタルケア | |||||
| 藤田 昌子 | |||||
| 兵庫県精神保健福祉センター主幹 | |||||
| 配付資料 | |||||
| 平成25年12月20日(金)
13:30〜15:00 |
「安全で安心なまちづくり」とは、「地域における、市民による、自律的・継続的に」<防災・減災>にとりくむ「環境改善運動」である。 そのために日々の防災環境改善運動として、<防災/防犯><景観/ゴミ><福祉/子育て>をベースにした「防災まちづくり」に取り組んでいくことが重要である。 | 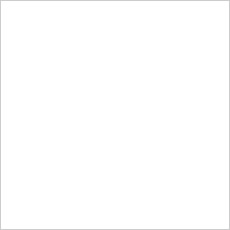 |
|||
| 安全安心のまちづくり | |||||
| 減災と準備、松本せせらぎと野田北ふるさとネット | |||||
| 小林 郁雄 | |||||
| (公財)ひょうご震災記念21世紀研究機構人と防災未来センター上級研究員 兵庫県立大学 緑環境景観マネジメント研究科特任教授 |
|||||
|
配付資料1 配付資料2 |
|||||
| 平成26年1月22日(水)
13:30〜15:00 |
東日本大震災を例に、要援護者(高齢者・障がい者・妊婦等)が避難・避難生活をする際に、地域や関係者がどのように支援を行ったかについて、主に宮城県南三陸町の避難所の聞き取り調査の結果もとにお話しします。また、日常から、地域や福祉関係者や行政や当事者団体等とどのように連携して備えておけばよいのかについて、いくつかの取り組みを紹介しながら考えていきます。 | 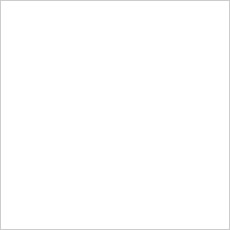 |
|||
| 災害時の要援護者支援 | |||||
| 津波避難、避難所での災害時要援護者支援、避難所自主運営、日常からの地域の取組み | |||||
| 石川 永子 | |||||
| (公財)ひょうご震災記念21世紀研究機構人と防災未来センター主任研究員 | |||||
| 配付資料 | |||||
平成26年1月29日(水)
|
東海、東南海・南海地震対策は、東日本大震災の発生を受け、大きな転機を迎えている。これまで考えてこなかった数千年に1回というような極めて低頻度で規模が巨大化するようなケースとどう向き合い、何をしていけばよいのか。「南海トラフ巨大地震」と名付けられた政府による新たな想定は、そうした規模の地震・津波に対しても避難の意識を持たせるために大いに有効であろう。一方で、そうした規模の地震・津波に対して安全・安心な地域づくりを推進していくことはできないだろうか。本講義では、柔軟性、強靱性、持続可能性をキーワードに、これからの南海トラフ巨大地震津波対策の可能性について論じる。 | 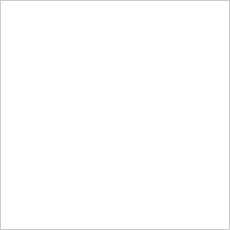 |
|||
| 南海トラフ巨大地震津波対策 | |||||
| 柔軟性,強靱性,持続可能性 | |||||
| 奥村 与志弘 | |||||
| (公財)ひょうご震災記念21世紀研究機構人と防災未来センターリサーチフェロー 京都大学大学院地球環境学堂助教 |
|||||
| 配付資料 | |||||