| 開催日・テーマ・講師 | 講義内容 | 配付資料 | |||
| 平成25年10月4日(金)
15:00〜16:30 |
経済状況・健康問題・人間関係などいわゆる多問題をかかえながらも、社会資源を活用出来ず、制度の狭間に埋没している人々が存在している。 個人の苦悩を社会の問題として、そのリスクを共に負い、克服していくことが、肝心である。 ひきこもりやゴミ家敷などを例に、共に生きる社会の創造にむけてどのような施策が望まれるのか考えてみたい。 | 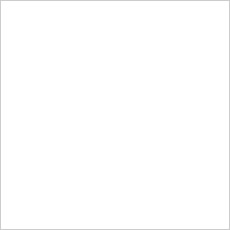 |
|||
| 社会的排除と「共生」 −包摂的コミュニティへの取り組み− | |||||
| 社会的排除/包摂、リスク制御、コミュニティ・ソーシャル・ワーカー | |||||
| 松原 一郎 | |||||
| (公財)ひょうご震災記念21世紀研究機構研究調査本部政策コーディネーター 関西大学社会学部教授 |
|||||
| 配付資料 | |||||
| 平成25年11月6日(水) 15:00〜16:30 |
阪神・淡路大震災を大きなきっかけとして制定されたNPO法(特定非営利活動促進法)成立から15年が経ち、さらに東日本大震災の復興支援におけるNPO等の活躍もあり、NPO・市民活動の認知度は近年飛躍的に高まってきている。 しかし、NPOは「民間による社会変革の担い手」「持続可能な事業体」にどこまでなっているだろうか。あるいは、「新たな働く場(社会的企業)」となっているだろうか。 また、わが兵庫は「NPO・市民活動の先進地」と自負している(?)が、本当にそうか。全国でどんどん新しい活動・事業が出てくる中で「周回遅れ」になっていないか。 この6月に設立された「公益財団法人ひょうごコミュニティ財団」(7月に公益認定)の事例をもとに、「寄付」「ボランティア」「NPO」「市民参加」などのキーワードを軸に、共生社会のあり方、それの中心的担い手の一つであるNPO等を支える基盤、とりわけ財政的基盤について考察します。 | 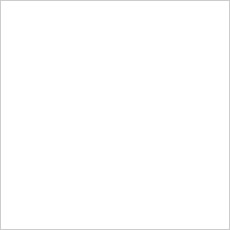 |
|||
| 市民がつくる共生社会 −「お金」がつなぐ寄付者と社会− | |||||
| NPO、財源、コミュニティ財団、寄付と助成金、地域社会 | |||||
| 実吉 威 | |||||
| 市民活動センター神戸理事・事務局長 ひょうごコミュニティ財団理事 |
|||||
| 配付資料 | |||||
| 平成25年11月22日(金) 15:00〜16:30 |
地域の再生には、多様な主体が政策に参画するとともに、それらのネットワークを活かしての協働が必要になっている。では、そのための具体的な施策とはどのようなものであろうか。地域経済の立場からは、コミュニティビジネスを活かすなど、市場経済の手法を用いて社会課題を解決する社会的経済についての議論を、また地域福祉の立場からは、課題の共有から新たな解決策を導く小地域開発など、コミュニティ・オーガナイゼーション(地域組織化)の議論を展開する。こうした議論を踏まえ、ガバナンスのあり方を考える。 | 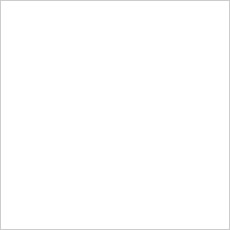 |
|||
| ローカル・ガバナンスの施策 −地域経済・福祉における参画と協働− | |||||
| コミュニティ・オーガナイゼーション、雇用創出、地域イノベーションシステム、社会的経済 | |||||
| 田端 和彦 | |||||
| 兵庫大学生涯福祉学部社会福祉学科教授 | |||||
| 配付資料 | |||||
| 平成25年12月6日(金) 15:00〜16:30 |
子ども系のNPO職員・事務局長を10数年歴任したのち、公募に応じて文部科学省生涯学習政策局専門職に転職(2011年5月〜2013年3月の2年間の任期付雇用)。 “外”から見ていた行政組織と、“中の人”となって感じる行政組織の違いや相似点、戸惑い、官民連携の在り方、行政職員の考え方、中央官庁と地方自治体の関係(特に文科省と教育委員会、学校現場)等、実体験に基づき、中央府省の論点と課題について講義します。 | 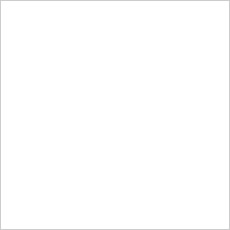 |
|||
| 行政とNPO −中央府省の論点と課題− | |||||
| NPOと行政の協働/連携、行政の下請け化、人材の流動化、セクター間の交流 | |||||
| 林 大介 | |||||
| 東洋大学社会学部社会福祉学科助教 | |||||
| 配付資料 | |||||
| 平成26年1月10日(金) 15:00〜16:30 |
1990年代の半ばから続く地方分権の進展を背景にコミュニティのあり方が問われるようになってきました。この問題は自治体では市民との協働として論じられています。そこなかでNPOなどのボランタリー・セクターのあり方も問われています。わたくしたちはわたくしたち自身の暮らしについての民主的なあり方と密接にかかわる問題です。この講義はボランタリー・セクターの民主的展望を議論したいと考えています。 | 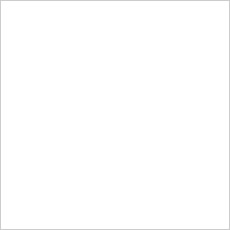 |
|||
| 分権社会における都市と自治 −ボランテリー・セクターの展望と論点− |
|||||
| 民主主義、分権改革、ボランタリー・セクター、都市自治 | |||||
| 南島 和久 | |||||
| 神戸学院大学法学部法律学科准教授 | 配付資料 | ||||
| 平成26年2月21日(金)
15:00〜16:30 |
シリーズのしめくくりとして、公共的領域の問題処理(リスク制御)を担う新たなシステムを実現することが、共生社会を目指すうえで不可欠であることを強調したい。
そのシステムとは市民の「参画」と他の部門(政府や市場)との「協働」から成るガバナンスを意味し、それは21世紀初期社会の文明を彩るひとつのかたちをなすべきものでもあろう。 |
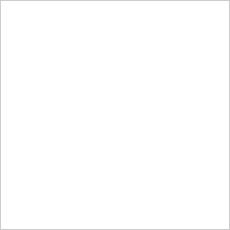 |
|||
| 共生社会の実現に向けて −ローカル・ガバナンスのかたち− | |||||
| 関わりと繋がり、コミュニティ政策、市民セクター | |||||
| 松原 一郎 | |||||
| (公財)ひょうご震災記念21世紀研究機構研究調査本部政策コーディネーター 関西大学社会学部教授 |
|||||
| 配付資料 | |||||